2022.07.29
海外便り№13 佐奈喜祐哉さん(Institut Curie)

佐奈喜 祐哉
JSPS 海外特別研究員
GENETICS AND PHYSIOLOGY OF GROWTH team
Institut Curie, Paris, France
JSPS 海外特別研究員
GENETICS AND PHYSIOLOGY OF GROWTH team
Institut Curie, Paris, France
こんにちは。フランス・パリのキュリー研究所でポスドクをしている佐奈喜です。 博士課程は京都大学生命の井垣達吏先生のもとでショウジョウバエ遺伝学をゼロから叩き込んでいただき、2018年からショウジョウバエ研究の巨匠とも言えるピエール・レオポルドのお世話になっています。4年目にもなると、私の中での海外研究生活の魅力やノウハウが見えてきたように思います。そこで、この海外だよりを読んでいる(おそらく研究留学についての情報収集を目的としている)方に向けて、本稿の前半では海外留学のケーススタディーを、後半ではフランスでの研究生活で得られたものについて紹介したいと思います。
海外留学ことはじめ
慣れ親しんだ母国を離れて海外留学を目指すとなると、高い心ざしで研究に打ち込むぞとの気合に満ち溢れているかと思います。研究留学をより充実したものにするために(トラブルを回避するために)は、小さなTipsが重要なように思います。海外留学を3ステップに分けたモデルをもとに、どうやって海外留学を始めるのか、どうすればベストの海外留学になるのかを考えていきたいと思います。
海外留学ことはじめ
慣れ親しんだ母国を離れて海外留学を目指すとなると、高い心ざしで研究に打ち込むぞとの気合に満ち溢れているかと思います。研究留学をより充実したものにするために(トラブルを回避するために)は、小さなTipsが重要なように思います。海外留学を3ステップに分けたモデルをもとに、どうやって海外留学を始めるのか、どうすればベストの海外留学になるのかを考えていきたいと思います。
海外留学ことはじめ
慣れ親しんだ母国を離れて海外留学を目指すとなると、高い心ざしで研究に打ち込むぞとの気合に満ち溢れているかと思います。研究留学をより充実したものにするために(トラブルを回避するために)は、小さなTipsが重要なように思います。海外留学を3ステップに分けたモデルをもとに、どうやって海外留学を始めるのか、どうすればベストの海外留学になるのかを考えていきたいと思います。
慣れ親しんだ母国を離れて海外留学を目指すとなると、高い心ざしで研究に打ち込むぞとの気合に満ち溢れているかと思います。研究留学をより充実したものにするために(トラブルを回避するために)は、小さなTipsが重要なように思います。海外留学を3ステップに分けたモデルをもとに、どうやって海外留学を始めるのか、どうすればベストの海外留学になるのかを考えていきたいと思います。

①行き先を決める
たとえ海外に行ったとしても、興味のない研究をしていては得られるものも少ないでしょう。行き先は、あなたのやりたいことのできる研究室レベルを選び出しましょう。アメリカは、サイエンスの中心と言われて目立ちますね。私も修士課程のころは、いつかはアメリカで研究をしてみたいと考えていましたが、自分の興味とベストフィットして、ご縁もあったことからフランスのピエール研究室を選びました。今までアメリカに行くために英会話を勉強してきたのに、まさかのフランス。失礼なことですが、行く前はフランスのサイエンスで大丈夫だろうかという心配もありましたが、結果としてはこれ以上ない大成功で、経験豊かなPIや興味を共有できる同僚から刺激を受けてプロジェクトを進めていけるのは楽しいことこの上ないです。
充実した海外留学を送るために、早いうちから自分の興味に任せて論文を読み漁り、これぞと思う研究を続けているラボのリストを作っておきましょう。もし、これといってそそられる研究室が見当たらない場合は、先輩や先生にどのラボや論文が好きか聞いてみるのも良い手だと思います。自分の知らなかった面白い研究分野が見つかるかもしれません。
行きたいところが定まり、学位取得が見えて来たなら、あとは当たって砕けろです。自分でメールを出してみる、学会で話しかけてみる、所属研究室の先生を通して探ってみるなど色々コンタクトの方法があると思います。向こうのラボのタイミングもあるので、断られても気にせずどんどん次の候補に移りましょう。もし、先方からも興味が示されると、CVと推薦書(2-3通)を送り、セミナー及びインタビューがセッティングされると思います。これまで頑張ってきたトークスキルや研究成果を存分に発揮してください。
ちなみに私の場合は、上村匡先生がピエールをセミナーに招待した時に、上村ラボの所属でもない私に昼ごはんに同行する機会をくださったことがきっかけでポスドク先が決まりました。巨匠ピエールの横でめちゃくちゃ緊張しながら刺身定食を食べていると、おもむろにピエールが「ポスドクを探している」と言い、私が「あなたのラボに行きたい」と言ったら決まりました。二言三言で決まってしまい、その後は刺身定食に付いていた日本式コロッケがうまいという話になったように記憶しています。さすが巨匠、度量が違うなと思いますが、こんなラッキーもあるので興味のあるラボ候補は常に考えておく、機会があればすぐに手を上げるよう心の準備をしておくと良いかもしれません。
たとえ海外に行ったとしても、興味のない研究をしていては得られるものも少ないでしょう。行き先は、あなたのやりたいことのできる研究室レベルを選び出しましょう。アメリカは、サイエンスの中心と言われて目立ちますね。私も修士課程のころは、いつかはアメリカで研究をしてみたいと考えていましたが、自分の興味とベストフィットして、ご縁もあったことからフランスのピエール研究室を選びました。今までアメリカに行くために英会話を勉強してきたのに、まさかのフランス。失礼なことですが、行く前はフランスのサイエンスで大丈夫だろうかという心配もありましたが、結果としてはこれ以上ない大成功で、経験豊かなPIや興味を共有できる同僚から刺激を受けてプロジェクトを進めていけるのは楽しいことこの上ないです。
充実した海外留学を送るために、早いうちから自分の興味に任せて論文を読み漁り、これぞと思う研究を続けているラボのリストを作っておきましょう。もし、これといってそそられる研究室が見当たらない場合は、先輩や先生にどのラボや論文が好きか聞いてみるのも良い手だと思います。自分の知らなかった面白い研究分野が見つかるかもしれません。
行きたいところが定まり、学位取得が見えて来たなら、あとは当たって砕けろです。自分でメールを出してみる、学会で話しかけてみる、所属研究室の先生を通して探ってみるなど色々コンタクトの方法があると思います。向こうのラボのタイミングもあるので、断られても気にせずどんどん次の候補に移りましょう。もし、先方からも興味が示されると、CVと推薦書(2-3通)を送り、セミナー及びインタビューがセッティングされると思います。これまで頑張ってきたトークスキルや研究成果を存分に発揮してください。
ちなみに私の場合は、上村匡先生がピエールをセミナーに招待した時に、上村ラボの所属でもない私に昼ごはんに同行する機会をくださったことがきっかけでポスドク先が決まりました。巨匠ピエールの横でめちゃくちゃ緊張しながら刺身定食を食べていると、おもむろにピエールが「ポスドクを探している」と言い、私が「あなたのラボに行きたい」と言ったら決まりました。二言三言で決まってしまい、その後は刺身定食に付いていた日本式コロッケがうまいという話になったように記憶しています。さすが巨匠、度量が違うなと思いますが、こんなラッキーもあるので興味のあるラボ候補は常に考えておく、機会があればすぐに手を上げるよう心の準備をしておくと良いかもしれません。
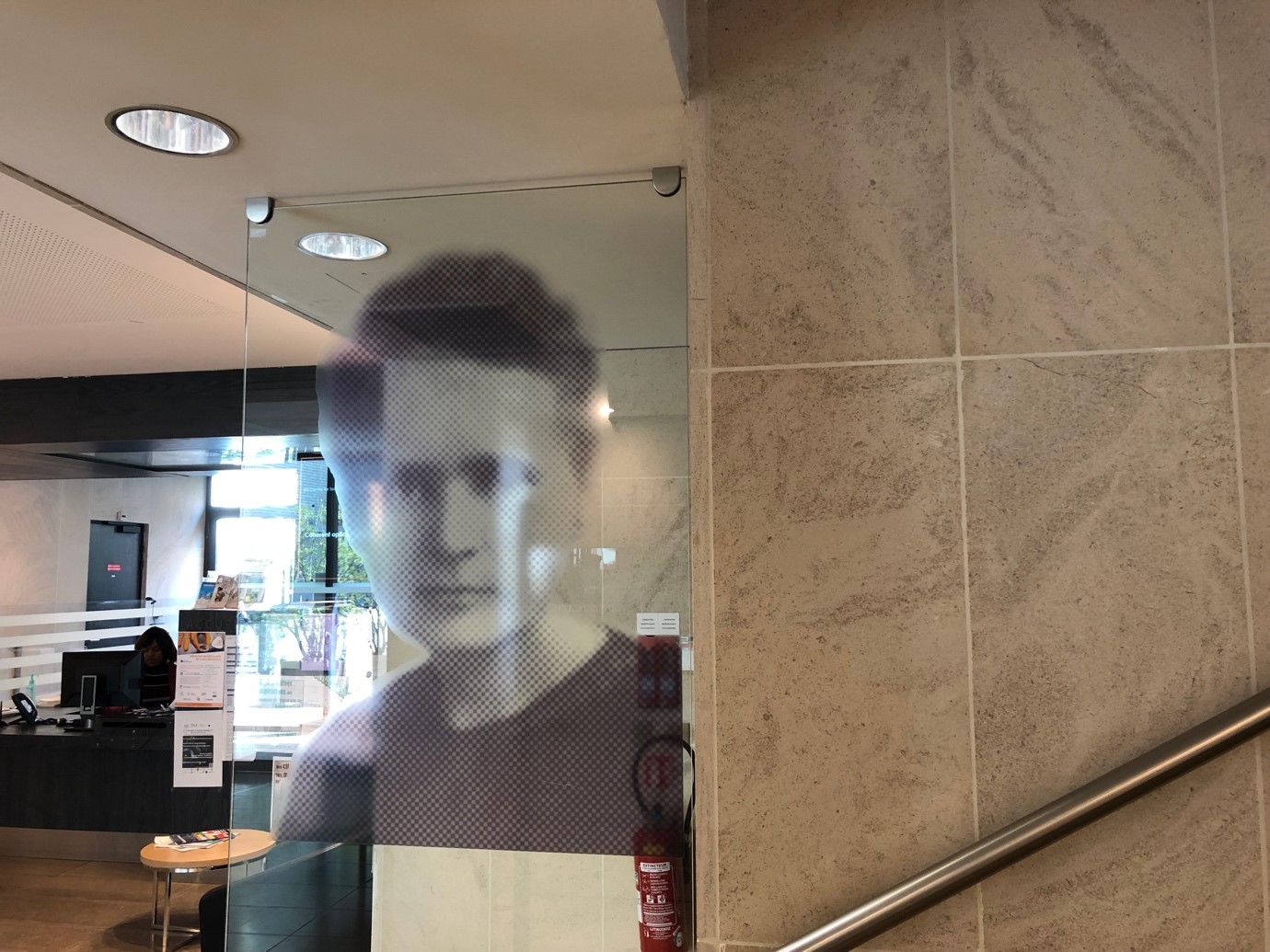
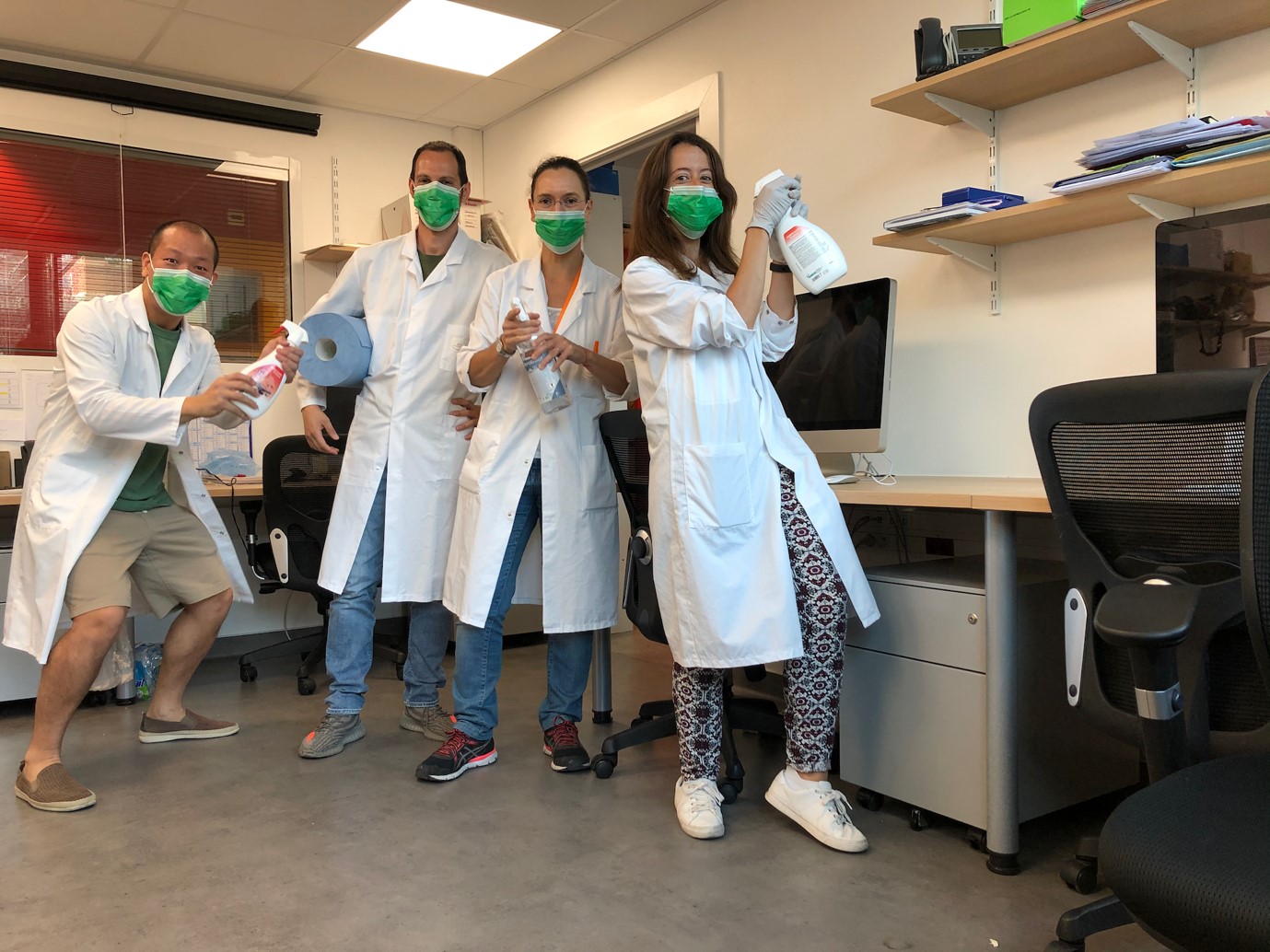
②フェローシップ
他の海外だよりでも触れられている通り、フェローシップの取得は歓迎されます。申請書を書くこと自体がトレーニングなので、たとえラボの研究費で雇われていても、チャレンジがしてみると良いと思います。私の場合は、1年目の海外学振は落とされ、ラボの研究費で養ってもらう間に結果を蓄え、2年目のチャレンジで無事に取ることができました。主なフェローシップは、海外学振・HFSP・Marie Curie・EMBO・渡航国先のグラント・日本からは内藤・上原・東洋紡・第一三共などが応募候補だと思います。海外学振以外は、学位をとった国からの移動が必須、共同研究実績がある研究室を行き先として認めないなどの制限や、学位取得後X年以内、移動してから2年目の応募不可など、さまざまな制限があるので注意が必要です。私はポスドクの間までに学位論文のためにピエール研究室と共同研究をしていたので海外学振しか選択肢が残されていませんでした。
海外学振はこちらでもユニークな制度なようで、一国が行き先の制限なくどの国でも研究生活をサポートする制度は他に見当たらないようです。マリーキュリーならヨーロッパ国内、HFSPなら参加国内など、多くのフェローシップには活動場所の制限がつきものですが、日本人なら行き先は問わず研究のために潤沢な資金を出してくれる海外学振は、とても恵まれているチャンスで、ありがたい限りです。ただ、海外だよりNo 11の川口さんもおっしゃられているように、手取りが半分になってしまうことがあります。海外学振に限らず、勤務先によっては雇用契約を結ぶ必要がり、社会保障や税金が引かれるためフェローシップ要項に記載されている額の半分が手取りとなることがあります。面白いことに、フランス国内であっても勤務先(大学や、ラボへの入室登録ない研究分野など)によっては雇用契約を求められず満額を手に入れられるようです。極めてケースバイケース、かつ今後制度が変わる可能性もあるのでフェローシップ応募前には必ずPIや事務に確認しましょう。もし、私のように手取り半分以下になったとしても快適に生活できます。その悔しさをバネに、より良い研究を目指していきましょう。
他の海外だよりでも触れられている通り、フェローシップの取得は歓迎されます。申請書を書くこと自体がトレーニングなので、たとえラボの研究費で雇われていても、チャレンジがしてみると良いと思います。私の場合は、1年目の海外学振は落とされ、ラボの研究費で養ってもらう間に結果を蓄え、2年目のチャレンジで無事に取ることができました。主なフェローシップは、海外学振・HFSP・Marie Curie・EMBO・渡航国先のグラント・日本からは内藤・上原・東洋紡・第一三共などが応募候補だと思います。海外学振以外は、学位をとった国からの移動が必須、共同研究実績がある研究室を行き先として認めないなどの制限や、学位取得後X年以内、移動してから2年目の応募不可など、さまざまな制限があるので注意が必要です。私はポスドクの間までに学位論文のためにピエール研究室と共同研究をしていたので海外学振しか選択肢が残されていませんでした。
海外学振はこちらでもユニークな制度なようで、一国が行き先の制限なくどの国でも研究生活をサポートする制度は他に見当たらないようです。マリーキュリーならヨーロッパ国内、HFSPなら参加国内など、多くのフェローシップには活動場所の制限がつきものですが、日本人なら行き先は問わず研究のために潤沢な資金を出してくれる海外学振は、とても恵まれているチャンスで、ありがたい限りです。ただ、海外だよりNo 11の川口さんもおっしゃられているように、手取りが半分になってしまうことがあります。海外学振に限らず、勤務先によっては雇用契約を結ぶ必要がり、社会保障や税金が引かれるためフェローシップ要項に記載されている額の半分が手取りとなることがあります。面白いことに、フランス国内であっても勤務先(大学や、ラボへの入室登録ない研究分野など)によっては雇用契約を求められず満額を手に入れられるようです。極めてケースバイケース、かつ今後制度が変わる可能性もあるのでフェローシップ応募前には必ずPIや事務に確認しましょう。もし、私のように手取り半分以下になったとしても快適に生活できます。その悔しさをバネに、より良い研究を目指していきましょう。
③プロジェクトを進める
さて、無事にポスドクを始めることができれば、あとはこっちのものです。フランスを含めて海外では日本と比べて分業や外注が整っているので、多くの時間を実験に注ぐことができます。NGSをセットアップし、インフォマティクスの人に解析してもらい、得られた知見からプロジェクトを進めていくことが一つの王道パターンのように思います。スクリーニングや新しい現象を探す最初のステップが大幅にスピードアップできるので、とても合理的で着実なプロジェクト進捗が期待できます。一方で見方を変えると、貴重なサンプルから面白いことを発見するのはインフォマティクスに任せて、解析結果という名の指示が飛んで来るだけのようにも感じます。更なる解析の組み立てはウエット研究者の腕の見せ所ですが、なんだか見逃していることが多いような気がしてなりません。データの元になった生命現象は実験者だけが生で見ていて、長年の積み重ねにもとづく細かい感覚はあなたにしかありません。効率的に進む共同研究ではスピードに圧倒されてしまいますが、パイプラインの吐き出すデータから何かを掘り出す探索こそがウエット研究者の経験が光るポイントだと思います。せっかく海外に来てまで追い求めている何か面白いことが、いつの間にかただの作業にならないように頑張りましょう。
さて、無事にポスドクを始めることができれば、あとはこっちのものです。フランスを含めて海外では日本と比べて分業や外注が整っているので、多くの時間を実験に注ぐことができます。NGSをセットアップし、インフォマティクスの人に解析してもらい、得られた知見からプロジェクトを進めていくことが一つの王道パターンのように思います。スクリーニングや新しい現象を探す最初のステップが大幅にスピードアップできるので、とても合理的で着実なプロジェクト進捗が期待できます。一方で見方を変えると、貴重なサンプルから面白いことを発見するのはインフォマティクスに任せて、解析結果という名の指示が飛んで来るだけのようにも感じます。更なる解析の組み立てはウエット研究者の腕の見せ所ですが、なんだか見逃していることが多いような気がしてなりません。データの元になった生命現象は実験者だけが生で見ていて、長年の積み重ねにもとづく細かい感覚はあなたにしかありません。効率的に進む共同研究ではスピードに圧倒されてしまいますが、パイプラインの吐き出すデータから何かを掘り出す探索こそがウエット研究者の経験が光るポイントだと思います。せっかく海外に来てまで追い求めている何か面白いことが、いつの間にかただの作業にならないように頑張りましょう。

④ポスドクからその先
理想的な環境で研究に打ち込んでいると、あっという間に数年が過ぎます。ポスドクは一生続けるものではなく、次のポジションにつなげなければならない現実を忘れそうになります。ある日突然、事務から「この国の法律で期限付き雇用は6年以上認められないので、来年は契約更新ができない」とメールが来るかもしれません。ある日突然、ボスから「ラボを再編したいのでお前はやめろ」とのお声がかかるかもしれません。青天の霹靂はいつも突然やってきます。備えあれば憂いなし。ポスドクを始めたら、少しずつ次のキャリアについて考えなければなりません。ここでは、フランスで見つけた日本にはないキャリアパスを紹介します。
フランスの研究予算配分機関にはCNRSやINSERMなどがありますが、日本と異なるのは予算配分機関が多くの研究者の雇用元になっている点です。その例として、海外だよりNo 2の後藤さんがINSERMのパーマネント研究者というポジションを獲得されていますね。パーマネント研究者は、別途PIポストに採用されればPIになれるし、気に入ったラボがあればPIにならず好きなだけ研究に打ち込むことができる面白いポジションです。予算取りや雑務はPIに任せ、プロジェクトに専念できるポジションはとても魅力的に見えます。ラボにとっても、経験豊富で長期間に渡り複数のプロジェクトを牽引してくれるパーマネント研究者は、とても貴重な人材なようです。また、パーマネントエンジニア(技官)と呼ばれるポジションも用意されています。技官と言ってもPhD取得者で、一つのプロジェクトを進めるよりも、実験そのものが好きな人が目指すポジションのようです。ラボ内のプロジェクトをあらゆる面でサポートしてくれる、心強いラボの救世主です。私も実際にパーマネントエンジニアの方と一緒に仕事をさせてもらう機会に恵まれましたが、とても優秀です。日本でいう助教以上の経験値の方に実験を任せられる、もしくは実験を教えてもらえることが、いかにプロジェクトの推進剤になるかは容易に想像できると思います。このパーマネント研究者・エンジニアというポジションはヨーロッパでも珍しいようですが、ラボのノウハウの宝庫であり生産性の要になっています。ちなみに、国の機関で雇用されているので、家庭の事情など理由は問わず国内の好きな大学やラボに転勤することができるという、ライフワークバランスの面でも非常な魅力的なポジションです。採用はナショナルセレクションになるので狭き門ですが、毎年各分野で若干名ずつ採用されているようです。海外では日本と異なるシステムが色々とあるので、留学によって理想の働き方が見つかるかもしれませんね。どの国であれ、日本との違いを身をもって知れる留学はその後の研究人生の貴重な糧になると思います。あまり臆せず、外に飛び出してみてはいかがでしょうか。
理想的な環境で研究に打ち込んでいると、あっという間に数年が過ぎます。ポスドクは一生続けるものではなく、次のポジションにつなげなければならない現実を忘れそうになります。ある日突然、事務から「この国の法律で期限付き雇用は6年以上認められないので、来年は契約更新ができない」とメールが来るかもしれません。ある日突然、ボスから「ラボを再編したいのでお前はやめろ」とのお声がかかるかもしれません。青天の霹靂はいつも突然やってきます。備えあれば憂いなし。ポスドクを始めたら、少しずつ次のキャリアについて考えなければなりません。ここでは、フランスで見つけた日本にはないキャリアパスを紹介します。
フランスの研究予算配分機関にはCNRSやINSERMなどがありますが、日本と異なるのは予算配分機関が多くの研究者の雇用元になっている点です。その例として、海外だよりNo 2の後藤さんがINSERMのパーマネント研究者というポジションを獲得されていますね。パーマネント研究者は、別途PIポストに採用されればPIになれるし、気に入ったラボがあればPIにならず好きなだけ研究に打ち込むことができる面白いポジションです。予算取りや雑務はPIに任せ、プロジェクトに専念できるポジションはとても魅力的に見えます。ラボにとっても、経験豊富で長期間に渡り複数のプロジェクトを牽引してくれるパーマネント研究者は、とても貴重な人材なようです。また、パーマネントエンジニア(技官)と呼ばれるポジションも用意されています。技官と言ってもPhD取得者で、一つのプロジェクトを進めるよりも、実験そのものが好きな人が目指すポジションのようです。ラボ内のプロジェクトをあらゆる面でサポートしてくれる、心強いラボの救世主です。私も実際にパーマネントエンジニアの方と一緒に仕事をさせてもらう機会に恵まれましたが、とても優秀です。日本でいう助教以上の経験値の方に実験を任せられる、もしくは実験を教えてもらえることが、いかにプロジェクトの推進剤になるかは容易に想像できると思います。このパーマネント研究者・エンジニアというポジションはヨーロッパでも珍しいようですが、ラボのノウハウの宝庫であり生産性の要になっています。ちなみに、国の機関で雇用されているので、家庭の事情など理由は問わず国内の好きな大学やラボに転勤することができるという、ライフワークバランスの面でも非常な魅力的なポジションです。採用はナショナルセレクションになるので狭き門ですが、毎年各分野で若干名ずつ採用されているようです。海外では日本と異なるシステムが色々とあるので、留学によって理想の働き方が見つかるかもしれませんね。どの国であれ、日本との違いを身をもって知れる留学はその後の研究人生の貴重な糧になると思います。あまり臆せず、外に飛び出してみてはいかがでしょうか。

海外留学で得られたもの
私が海外留学を考え始めたのは学部3年か4年くらいだったと思います。聞き齧った話や周りの先生がたの経歴をみて、学位取得後はアメリカに行くものだと思っていました。博士課程になっても、まあ学位を取ったらどこか外国でポスドクをしようくらいにしか考えておらず、何か目標があったわけではありません。実際に、いざフランスに発つタイミングになっても、海外留学するという意義を見出せず、巨匠ピエールと一緒に働いてみたい、良いワインをいっぱい飲みたいくらいしかフランスに行く意味は思いつきませんでした。4年経った今でも、日本のラボとは違う文化や思考で研究が進むことを体験しましたが、海外は素晴らしい!日本のラボはダメだ!のような鮮烈な印象を得るには至っていません。どちらにも良い面と悪い面があるなかで、日本のラボも海外のラボも学生やポスドクとして働くには満足でした。
ここまで書いてみると、特に目標なく海外に行ってしまうと異文化に触れる機会にしかならないように思えますが、私にとっての海外留学ハイライトはピエールと働けたことだと思っています。巨匠なだけあり、日本人もびっくりの長時間労働でフランスアカデミーや研究所の仕事をされるなかでも、実験結果を聞くと「面白いね!次はどうするか?」と気持ちよくディスカッションしている姿を見ると、彼にとってサイエンスがいかに大きなモチベーションなのかと思い知らされます。俗にサイエンスへの情熱が強いPIは人間性を失っているということがあるかもしれませんが、ピエールはサイエンスの厳しさよりも楽しさに重きを置いているようです。この姿勢は、一生見習わなければならないと気付かされました。サイエンスへの情熱だけでなく、彼の人柄を伺わせるエピソードも事欠きません。どれだけ大量の仕事を抱えていてもラボメンバーや研究コミュニティに対してとてもサポーティブで、プロジェクトやキャリアパスだけでなく、頻発するさまざまな事務的トラブルに対しても、とても親身に時間をかけて話し合い、鮮やかに(時には苦労を重ねて)解決してみせる姿は心打たれるものがありました。この辺りは海外だよりNo 5の堀さんの記事と重なるものがあるかと思いますが、この人と働けたからこそ自分の中のロールモデルが激変したという経験はなかなか得難いものだと思います。もちろん日本にも多くの素晴らしい先生がいて、博士課程でお世話になる先生がロールモデルの中心になるだろうと思います。ただ、研究者は世界中にいます。日本にとどまり、隣の人と似たようなロールモデルしか持てないのも少しもったいないような気がしませんか?母国の日本で得られた経験と、好きなところに飛んでいって得られる経験をミックスしたオリジナルのロールモデルが出来上がってくるのは楽しいものです。ぜひ、海外留学にチャレンジしてみてください。
私が海外留学を考え始めたのは学部3年か4年くらいだったと思います。聞き齧った話や周りの先生がたの経歴をみて、学位取得後はアメリカに行くものだと思っていました。博士課程になっても、まあ学位を取ったらどこか外国でポスドクをしようくらいにしか考えておらず、何か目標があったわけではありません。実際に、いざフランスに発つタイミングになっても、海外留学するという意義を見出せず、巨匠ピエールと一緒に働いてみたい、良いワインをいっぱい飲みたいくらいしかフランスに行く意味は思いつきませんでした。4年経った今でも、日本のラボとは違う文化や思考で研究が進むことを体験しましたが、海外は素晴らしい!日本のラボはダメだ!のような鮮烈な印象を得るには至っていません。どちらにも良い面と悪い面があるなかで、日本のラボも海外のラボも学生やポスドクとして働くには満足でした。
ここまで書いてみると、特に目標なく海外に行ってしまうと異文化に触れる機会にしかならないように思えますが、私にとっての海外留学ハイライトはピエールと働けたことだと思っています。巨匠なだけあり、日本人もびっくりの長時間労働でフランスアカデミーや研究所の仕事をされるなかでも、実験結果を聞くと「面白いね!次はどうするか?」と気持ちよくディスカッションしている姿を見ると、彼にとってサイエンスがいかに大きなモチベーションなのかと思い知らされます。俗にサイエンスへの情熱が強いPIは人間性を失っているということがあるかもしれませんが、ピエールはサイエンスの厳しさよりも楽しさに重きを置いているようです。この姿勢は、一生見習わなければならないと気付かされました。サイエンスへの情熱だけでなく、彼の人柄を伺わせるエピソードも事欠きません。どれだけ大量の仕事を抱えていてもラボメンバーや研究コミュニティに対してとてもサポーティブで、プロジェクトやキャリアパスだけでなく、頻発するさまざまな事務的トラブルに対しても、とても親身に時間をかけて話し合い、鮮やかに(時には苦労を重ねて)解決してみせる姿は心打たれるものがありました。この辺りは海外だよりNo 5の堀さんの記事と重なるものがあるかと思いますが、この人と働けたからこそ自分の中のロールモデルが激変したという経験はなかなか得難いものだと思います。もちろん日本にも多くの素晴らしい先生がいて、博士課程でお世話になる先生がロールモデルの中心になるだろうと思います。ただ、研究者は世界中にいます。日本にとどまり、隣の人と似たようなロールモデルしか持てないのも少しもったいないような気がしませんか?母国の日本で得られた経験と、好きなところに飛んでいって得られる経験をミックスしたオリジナルのロールモデルが出来上がってくるのは楽しいものです。ぜひ、海外留学にチャレンジしてみてください。


