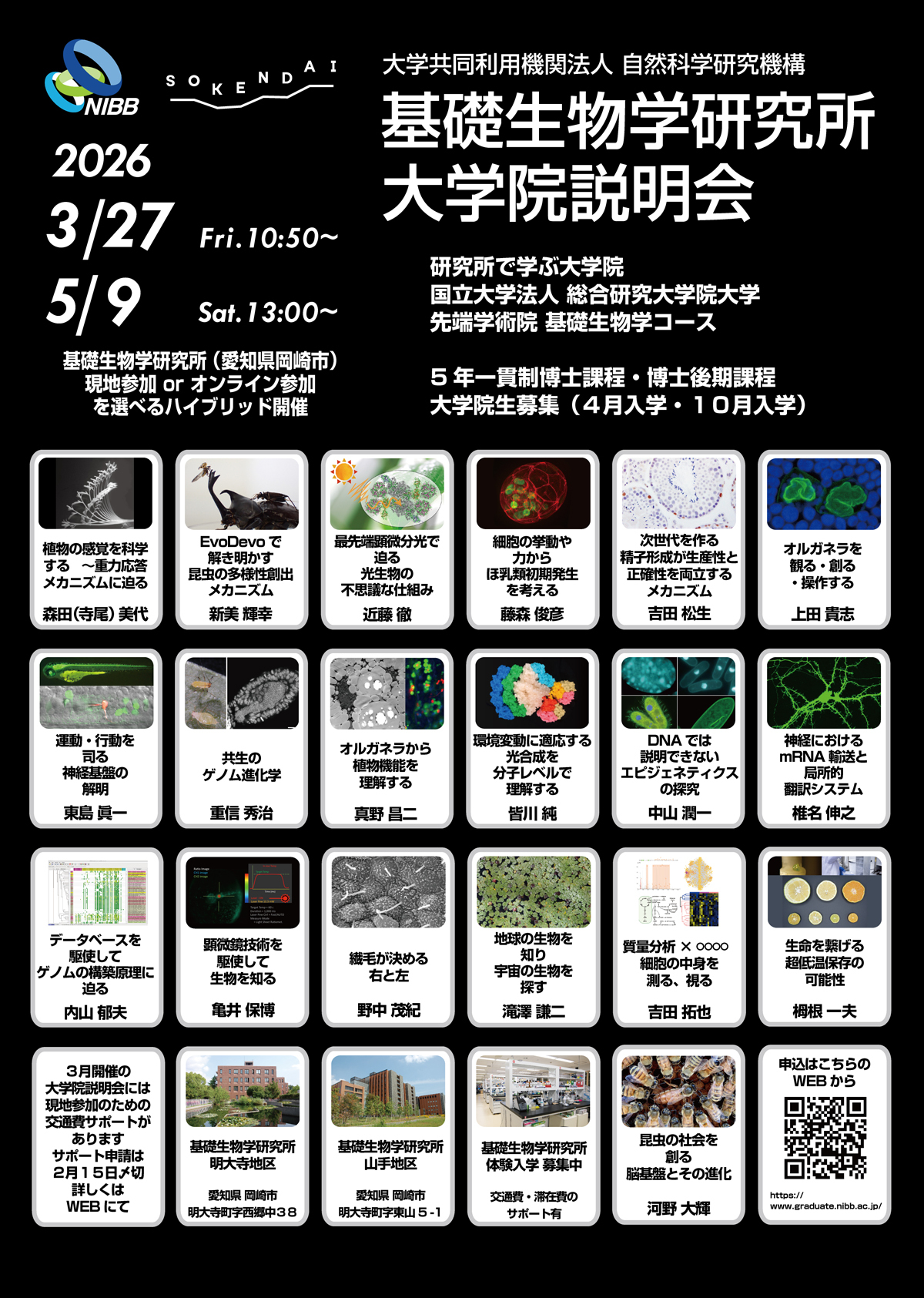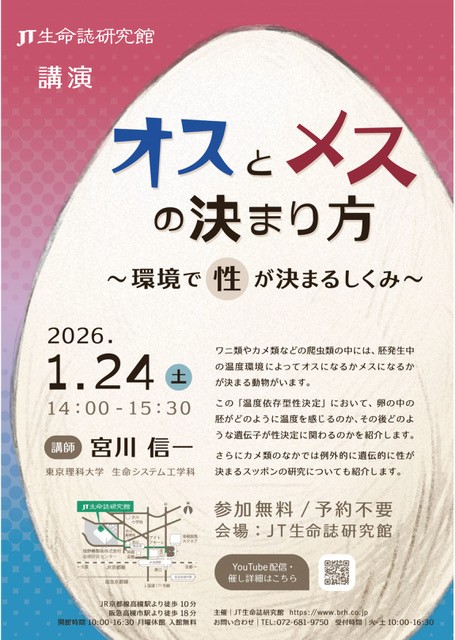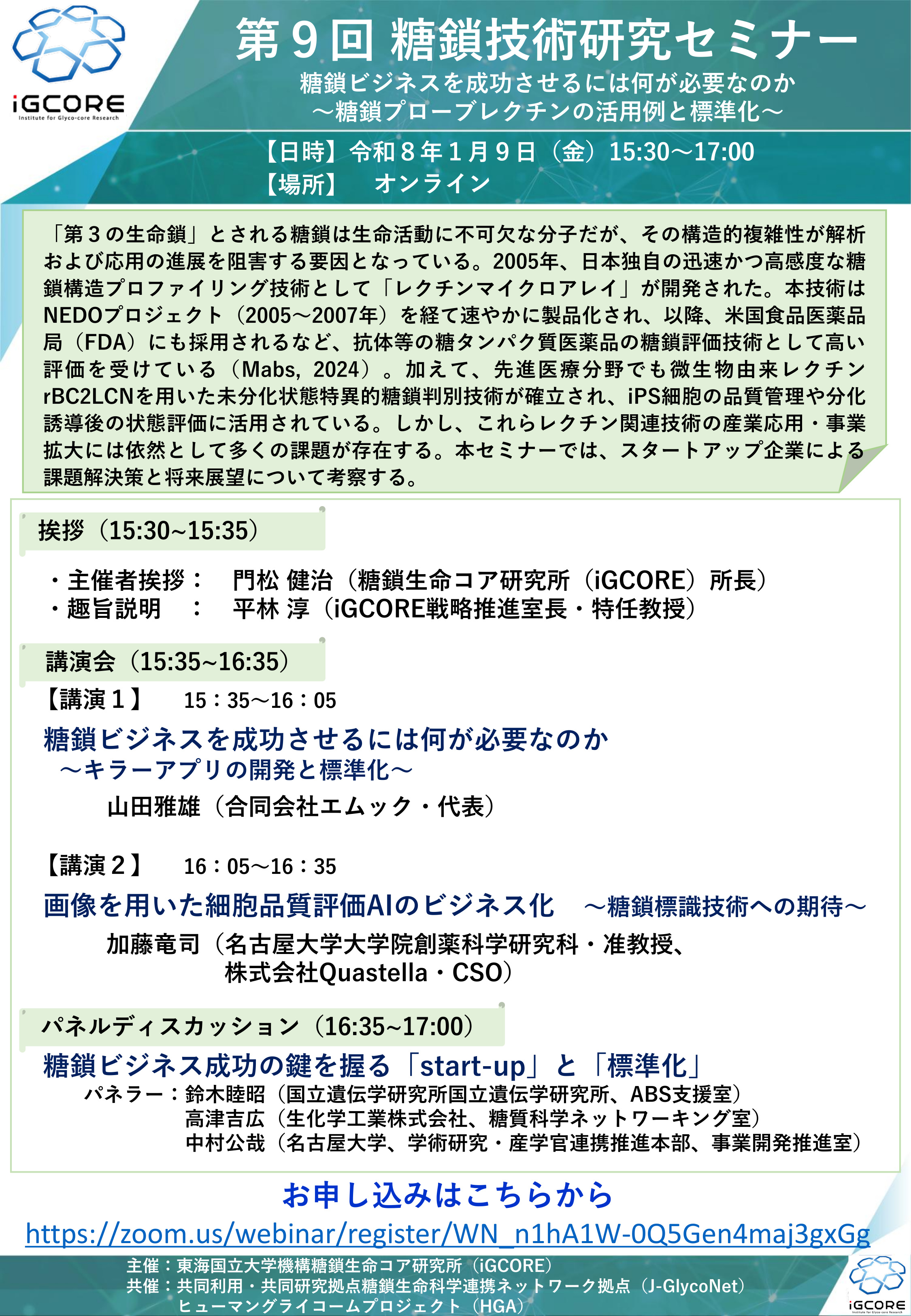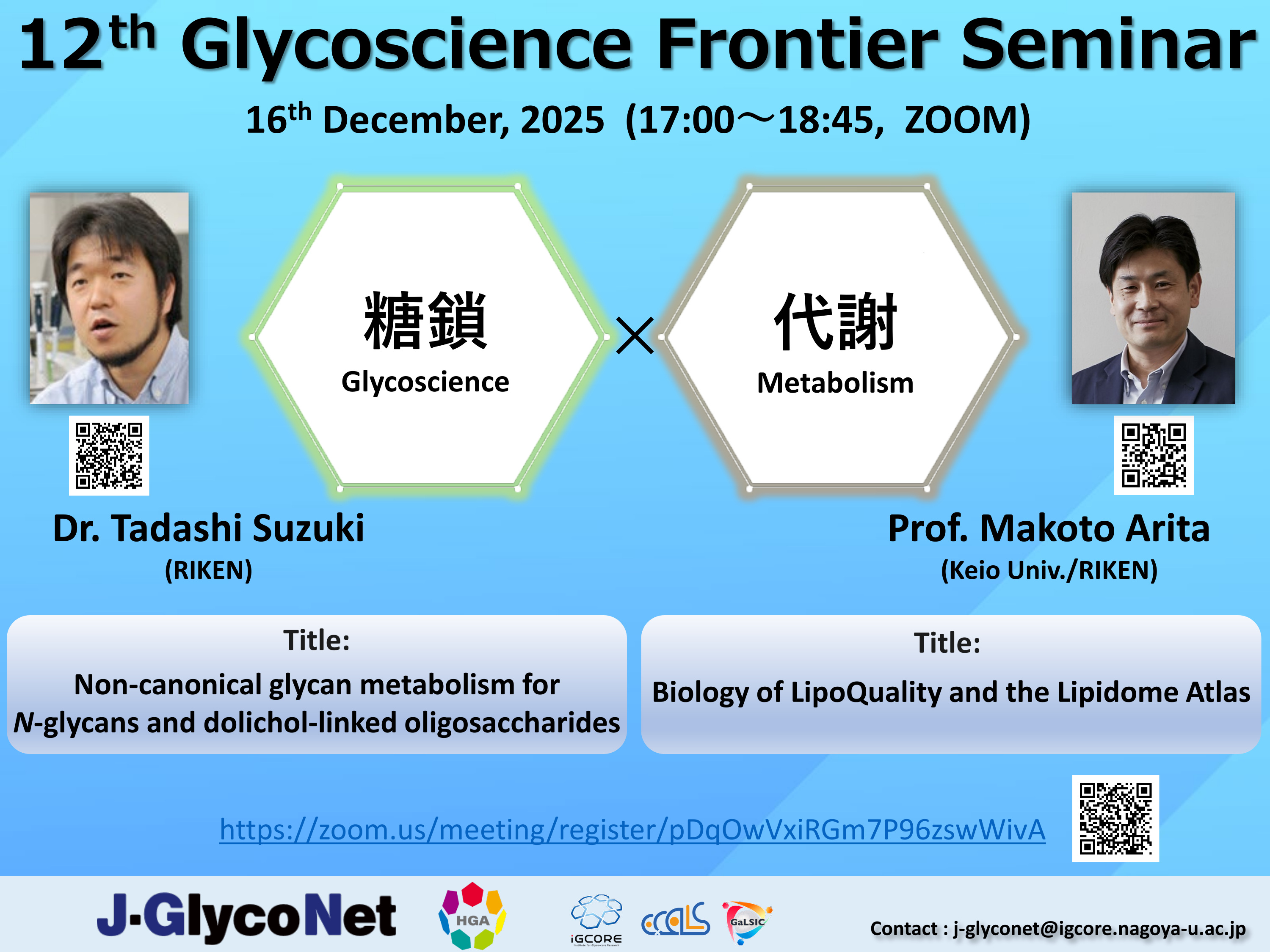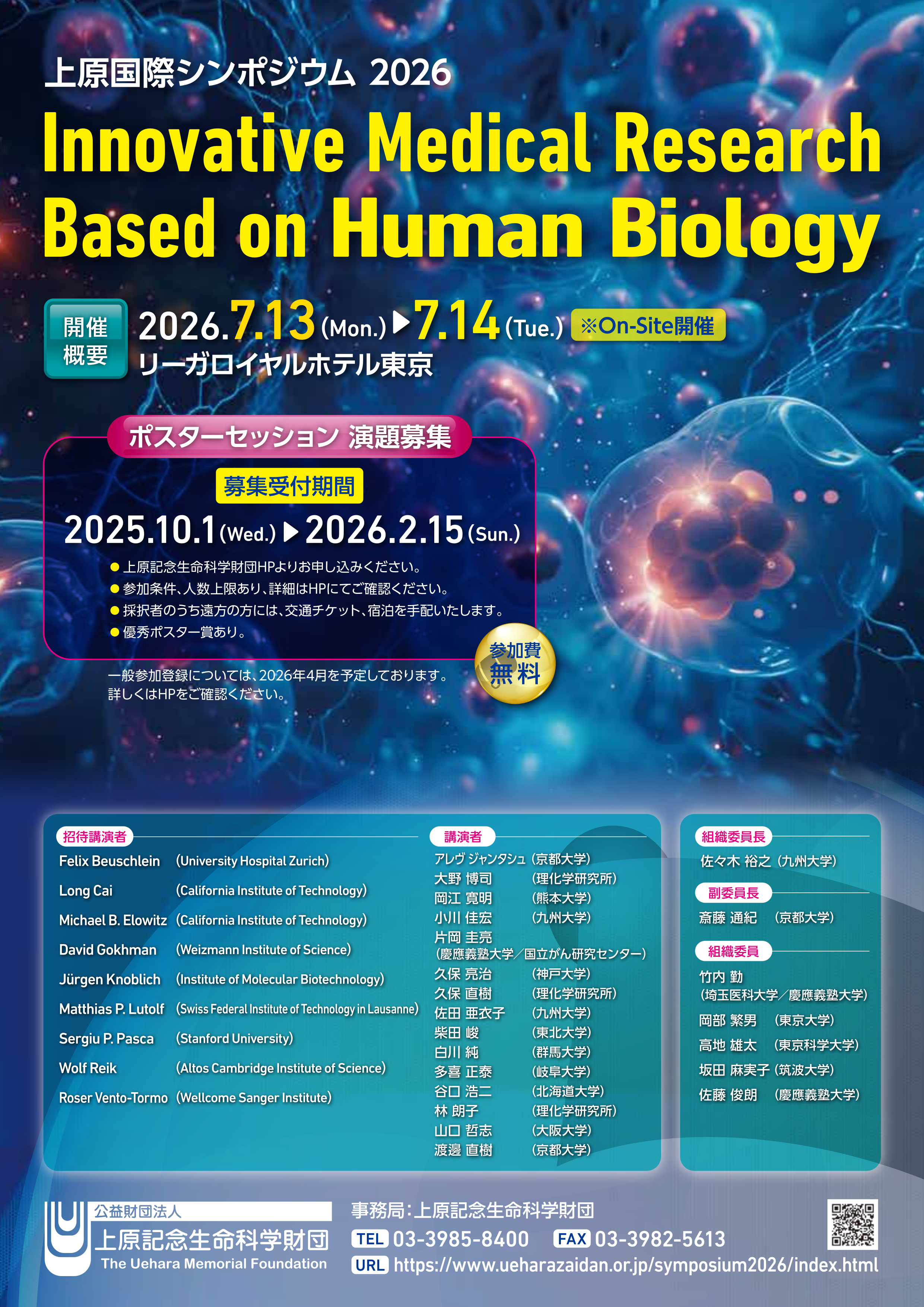2026.01.20
情報解析講習会のご案内<2025年度 PAGS・DDBJ合同 中級者情報解析講習会>
「先進ゲノム支援」では支援活動の一環として情報解析講習会を開催しています。今年度第2回目となる今回は、中級者向けです。プログラミング言語「Python」を用いたバイオインフォマティクス解析データの扱いやシングルセルRNA-seq解析の基礎等を中心に、以下の要領で開催いたします。本講習会は、先進ゲノム支援(PAGS)、生命情報・DDBJセンター(DDBJ)が合同で開催いたします。
■日 時:2026年2月20日(金)10:00 ~ 16:00(予定)
■会 場: Zoomウェビナー ※現地開催はございません。
■想定スキルレベル:情報解析中級者
■募集人員:オンライン参加:200名程度
·これから自分で実践的にバイオインフォマティクス関連のプログラミングをしようと考えている方。
·基本的なLinuxコマンドやPython言語の知識を身につけていることを前提とします。
·応募者多数の場合は、先進ゲノム支援における支援依頼者を優先します。
·各自のPCをご用意ください(memory8GB以上、空きHDD容量30GB以上あれば、Windows11、Mac、Linuxいずれも可)。
·講習ではJupyter notebookを用いてPythonの講習を行います。
·事前に必要なソフトウェア (Pythonのモジュール)を各自のPCにインストールしていただく必要があります。
■参加費用:無料
■講習会スケジュール(予定):講習内容とスケジュールは多少変更になる場合があります。
【2月20日】
10:00~10:05 講習会説明
10:05~10:30 Jupyter notebook の使い方
10:30~11:00 Numpy
11:00~12:00 表形式ファイルの処理(Pandas)
12:00〜13:00 昼食休憩
13:00〜14:30 Pythonを用いた基礎的なシングルセルRNA-seq解析
14:30〜14:40 休憩
14:40〜15:40 生成AIを用いたプログラミング等
15:40~16:00 質疑応答
■申し込み〆切:2026年2月9日(月)
■申し込み方法:
参加を希望される方は、下記リンクより詳細をご確認の上お申し込みください。
https://www.genome-sci.jp/bioinformatic#1
■日 時:2026年2月20日(金)10:00 ~ 16:00(予定)
■会 場: Zoomウェビナー ※現地開催はございません。
■想定スキルレベル:情報解析中級者
■募集人員:オンライン参加:200名程度
·これから自分で実践的にバイオインフォマティクス関連のプログラミングをしようと考えている方。
·基本的なLinuxコマンドやPython言語の知識を身につけていることを前提とします。
·応募者多数の場合は、先進ゲノム支援における支援依頼者を優先します。
·各自のPCをご用意ください(memory8GB以上、空きHDD容量30GB以上あれば、Windows11、Mac、Linuxいずれも可)。
·講習ではJupyter notebookを用いてPythonの講習を行います。
·事前に必要なソフトウェア (Pythonのモジュール)を各自のPCにインストールしていただく必要があります。
■参加費用:無料
■講習会スケジュール(予定):講習内容とスケジュールは多少変更になる場合があります。
【2月20日】
10:00~10:05 講習会説明
10:05~10:30 Jupyter notebook の使い方
10:30~11:00 Numpy
11:00~12:00 表形式ファイルの処理(Pandas)
12:00〜13:00 昼食休憩
13:00〜14:30 Pythonを用いた基礎的なシングルセルRNA-seq解析
14:30〜14:40 休憩
14:40〜15:40 生成AIを用いたプログラミング等
15:40~16:00 質疑応答
■申し込み〆切:2026年2月9日(月)
■申し込み方法:
参加を希望される方は、下記リンクより詳細をご確認の上お申し込みください。
https://www.genome-sci.jp/bioinformatic#1