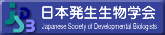Program
- Plenary lectures
- Symposia
- Symposium 1: Stem Cells, Regeneration
- Symposium 2: Neural development and network formation
- Symposium 3: Disease models and the new technology in fish science
- Symposium 4: Origin of vertebrates from developmental perspectives
- Symposium 5: Early Development
- Symposium 6: RNA and Development
- Symposium 7: Stem Cell Regulation: niche and signaling
- Workshops
- Workshop 1: Morphogenesis (axis formation, segmentation, etc)
- Workshop 2: Organogenesis
- Workshop 3: Neural development & behaviour and neural circuit development
- Workshop 4: Signalling in development
- Workshop 5: Cell biology of development (growth control, adhesion, migration)
- Workshop 6: Reproduction & gametology
- Workshop 7: Evolution and development
- Workshop 8: Stem cells and pluripotency, regeneration
- Poster presentations
- Luncheon seminars
- Gender-equal society (in Japanese)
- Satellite workshops organized by junior members (in Japanese)
- Public lectures (in Japanese)
| Plenary lectures |
| 29 May, 09:00 - 12:00, Room A |
| Plenary lectures 1 |
| PL1-01: 09:00-10:00 |
Developmental Genomics of Ciona intestinalis ○Noriyuki Satoh (Dept. Zool., Kyoto Univ. & OIST) |
|
| Chairperson: Kazuhiro W. Makabe (Universtiy of Tokushima) | ||
| PL1-02: 10:00-11:00 |
Cis-sequence regulation and its evolution in vertebrate Otx2 gene ○Shinichi Aizawa (Center for Developmental Biology (CDB), RIKEN Kobe) |
|
| Chairperson: Yumiko Saga (Nat'l Inst.of Genetics) | ||
| PL1-03: 11:00-12:00 |
The diversity and biomimetics of optical devices in nature ○Andrew Parker (University of Oxford) |
|
| Chairperson: Sumihare Noji (University of Tokushima) | ||
| 29 May, 13:10 - 15:10, Room A |
| Plenary lectures 2 |
| PL2-01: 13:10-14:10 |
Cell Shape Regulation by Cell Adhesion Machinery ○Masatoshi Takeichi (CDB) |
|
| Chairperson: Shinichi Aizawa (CDB, RIKEN) | ||
| PL2-02: 14:10-15:10 |
Integrating the BMP/DPP and Wnt signaling pathways at the level of Smad1/Mad phosphorylations ○Eddy M. De Robertis (HHMI/UCLA) |
|
| Chairperson: Naoto Ueno (Nat'l Inst.for Basic Biol.) | ||
| Symposia |
| 28 May, 9:00 - 12:00 |
|
Symposium 1: Stem Cells, Regeneration Organizer: Kiyokazu Agata Room: A |
| S1-01: 09:00-09:25 | The stem cell system in sponge: studies using asexual reproduction system as a model system ○Noriko Funayama (Dept. of Biophys., Graduate School of Science, Kyoto Univ.) | |
| S1-02: 09:25-09:55 | Stem Cells in Immortal Hydra ○Thomas Bosch (Christian-Albrechts-University Kiel) | |
| S1-03: 09:55-10:20 | New view of planarian stem cell system ○Norito Shibata (Dept. of Biophys, Kyoto Univ.) | |
| S1-04: 10:20-10:45 | Origin of germline and somatic stem cells in Oligochaeta, Annelida ○Shin Tochinai (Dept Nat Hist Sci, Fac Sci, Hokkaido Univ) | |
| S1-05: 10:45-11:10 | Stem cells and transdifferentiation in colonial tunicates ○Kazuo Kawamura, Takeshi Sunanaga (Kochi University) | |
| S1-06: 11:10-11:35 | Molecular basis for proximodistal respecification in insect leg regeneration ○Taro Mito1, Taro Nakamura1, Tetsuya Bando2, Hideyo Ohuchi1, Sumihare Noji1,2 (Dept. Life Systems, Inst. Tech. and Sci. Univ. Tokushima1, Tokushima Intellectual Cluster, Univ. Tokushima2) | |
| S1-07: 11:35-12:00 | Patterning-deficient limb regeneration in Xenopus ○Koji Tamura, Nayuta Yakushiji, Shiro Ohgo, Hitoshi Yokoyama (Grad. Sch. of Life Sci., Tohoku Univ.) | |
|
Symposium 2: Neural development and network formation Organizer: Noriko Osumi Room: B |
| S2-01: 09:00-09:40 | The cell biology of neural stem and progenitor cells ○Wieland B. Huttner (Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany) | |
| S2-02: 09:40-10:10 | Regulation of cell cycle parameters and cortical patterning by FGF receptor 3 ○Tomoko Iwata (Division of Cancer Sciences and Molecular Pathology, University of Glasgow) | |
| S2-03: 10:10-10:40 | Role of semaphorin/plexin signal in the developing nervous system ○Fumikazu Suto (Div. of Develop. Neurosci., Tohoku Univ. Grad. Sch. of Med.) | |
| S2-04: 10:40-11:10 | Long-term labeling and ablation reveal requirement of continuous neurogenesis for the structural and functional integrity of the adult forebrain ○Itaru Imayoshi, Ryoichiro Kageyama (IVR) | |
| S2-05: 11:10-11:50 | The role of Pax6 and its downstream molecules in embryonic and postnatal neurogenesis ○Noriko Osumi (Dept.of Dev.Neurobiol., Tohoku Univ.Grad.Sch.of Med.) | |
|
Symposium 3: Disease models and the new technology in fish science Organizers: Akira Kudo, Hiroyuki Takeda Room: C |
| S3-01: 09:00-09:50 | Endodermal organ development and regeneration ○Didier Stainier (UCSF) | |
| S3-02: 09:50-10:15 | A mutant medaka fish identifies a novel cytoplasmic protein responsible for human primary ciliary dyskinesia ○Hiroyuki Takeda (Dept. of Biol. Sci., University of Tokyo) | |
| S3-03: 10:15-10:40 | Vertebral bone formation in Medaka ○Akira Kudo (Dept.Biol.Inf., Tokyo Inst.Technol.) | |
| S3-04: 10:40-11:05 | Development of thymus and T lymphocytes in medaka ○Yousuke Takahama, Norimasa Iwanami (Univ Tokushima) | |
| S3-05: 11:05-11:30 | What guides blood and lymph vessels to the gross anatomical structure? ○Sumio Isogai1,2, Eiji Kimura1, Brant Weinstein2, Karina Yaniv2, Jiro Hitomi1 (IMU1, NICHD, NIH2) | |
| S3-06: 11:30-11:55 | Inactivation of Medaka Genes by Target-Selected Mutagenesis. ○Yoshihito Taniguchi1, Atsushi Toyoda2, Yoshiyuki Sakaki2, Shunichi Takeda1 (Kyoto Universtiy1, RIKEN GSC2) | |
|
Symposium 4: Origin of vertebrates from developmental perspectives Organizer: Shigeru Kuratani Room: D |
| S4-01: | Evolutionary changes in developmental patterns and processes towards gnathostomes ○Shigeru Kuratani (CDB, RIKEN) | |
| S4-02: | Evolutionary origin of the vertebrate lung ○Masataka Okabe (Dept. of Anat., Jikei Univ. School of Med.) | |
| S4-03: | Evolution of vertebrate fins and limbs ○Mikiko Tanaka (Grad.Sch.of Biosci.& Biotechnol., Tokyo Inst.of Technol.) | |
| S4-04: | Morphological evolution and physiological evolution: a molecular basis for ascidian’s “simple” tadpole to fluently swim ○Atsuo Nishino1,2, Shoji Baba3, Yasushi Okamura2,4 (Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Osaka Univ.1, Okazaki Inst. for Integr. Biosci., Natl. Inst. of Nat. Sci.2, Dept. of Adv. Biosci., Grad. Sch. of Hum. & Sci., Ochanomizu Univ.3, Dept. of Physiol., Grad. Sch. of Med., Osaka Univ.4) | |
| S4-05: | A systems biology approach to ascidian early development: how many ways to make a tadpole? ○Patrick Lemaire (IBDML) | |
| 30 May, 9:00 - 12:00 |
|
Symposium 5: Early Development Organizers: Masahiko Hibi, Hiroshi Sasaki Room: A |
| S5-01: 09:00-09:32 | Tead4 is required for specification of trophectoderm in pre-implantation mouse embryos Noriyuki Nishioka1, Shinji Yamamoto1, Kenjiro Adachi2, Hiroshi Kiyonari3, Mitsunori Ota1, KEN-ICHI Inoue3, Hiroko Sato1, Atsushi Sawada1, Kazuki Nakao3, Hitoshi Niwa2, ○Hiroshi Sasaki1 (Lab. Emb. Ind., RIKEN CDB1, Lab. Pluri. Cell Studies, RIKEN CDB2, LARGE, RIKEN CDB3) | |
| S5-02: 09:32-10:04 | Origin of body axis in the mouse embryo ○Hiroshi Hamada (Osaka University) | |
| S5-03: 10:04-10:36 | Physical forces generated by cells and sensed by cells. Yasuyuki Kida, Shuhei Kakizaki, Kota Miyasaka, Minoru Omi, ○Toshihiko Ogura (IDAC) | |
| S5-04: 10:36-11:08 | Roles of the PCP gene prickle in vertebrate development ○Naoto Ueno (NIBB) | |
| S5-05: 11:08-12:00 | Genetic regulation of gastrulation in zebrafsih ○Lilianna Solnica-Krezel, Christina Speirs, Diane Sepich, Isabelle Roszko, Simon Wu (Vanderbilt) | |
|
Symposium 6: RNA and Development Organizer: Haruhiko Siomi Room: B |
| S6-01: | Widespread evasion of post-transcriptional regulation by tandem UTR shortening associated with proliferative programs. ○Joel Neilson1, Phillip Sharp1, Rickard Sandberg2, Christopher Burge2, Arup Sarma3 (MIT Center for Cancer Research1, MIT Department of Biology2, MIT Department of Computer Science and Engineering3) | |
| S6-02: | RNA-directed DNA elimination in Tetrahymena ○Kazufumi Mochizuki (IMBA) | |
| S6-03: | A plant germline-specific Argonaute is required for maintenance of germline cell identity and meiosis progression ○Ken-Ichi Nonomura1,2, Mutsuko Nakano1, Mitsugu Eiguchi1, Akio Miyao3, Hirohiko Hirochika3, Nori Kurata1,2 (NIG1, SOKENDAI2, NIAS3) | |
| S6-04: | RNA-binding protein Nanos2 promotes male germ cell development by preventing female genetic program Suzuki Atsushi2, Rie Saba1, ○Yumiko Saga1 (NIG1, Yokohama National University, IRC2) | |
| S6-05: | Different types of small RNAs and Argonautes are utilized to repress retrotransposons in germline and somatic cells ○Haruhiko Siomi1,2 (Institute for Genome Research, University of Tokushima1, Department of Molecular Biology, Keio University School of Medicine2) | |
| S6-06: | brain tumor Interacts with dfmr1 to Regulate Neuromuscular Synapse Development ○Yong Q Zhang (IGDB, CAS) | |
|
Symposium 7: Stem Cell Regulation: niche and signaling Organizers: Miho Asaoka, Toru Nakano Room: C |
| S7-01: 09:00-09:35 | Hair graying, melanocyte stem cells and their niche ○Emi Nishimura (Dept. of Stem Cell Medicine,Cancer Research Institute, Kanazawa University) | |
| S7-02: 09:35-10:10 | Quiescence of Hematopoietic Stem Cells ○Toshio Suda (KEIO UNIV. SCH OF MED) | |
| S7-03: 10:10-10:50 | Stem cell niches and niche signaling ○Linheng Li (Stowers Institute) | |
| S7-04: 10:50-11:25 | Germline-stem-cell-niche formation in Drosophila male gonads ○Yu Kitadate, Satoru Kobayashi (NIBB) | |
| S7-05: 11:25-12:00 | Germline Stem Cell Formation in the Drosophila ovary ○Miho Asaoka (Dept. of Developmental Genetics, NIG) | |
| Workshops |
| 28 May, 13:10 - 17:15 |
| Workshop 1: Morphogenesis (axis formation, segmentation, etc) | |
| Organizers: (In the first half) |
Yoshiko Takahashi (Nara Institute of Science and Technology), Erina Kuranaga (University of Tokyo) |
| Organizers: (In the latter half) |
Koichi Kawakami (National Institute of Genetics), Atsuo Kawahara (National Cadiovascular Center Research Institute) |
| Room: A | |
| W1-01: 13:10-13:25 | Coordination of cell polarity during Xenopus gastrulation ○Asako Shindo, Takamasa Yamamoto, Naoto Ueno (NIBB) | |
| W1-02: 13:25-13:40 | Ectodermal specification by a novel transcroptional modulator ○Noriaki Sasai, Rieko Yakura, Daisuke Kamiya, Yoko Nakazawa, Yoshiki Sasai (RIKEN Ctr.for Dev.Biol.) | |
| W1-03: 13:40-13:55 | Functional importance and evolutional conservation of Tbx6 binding sites in presomitic mesoderm (PSM) specific enhancer of Mesp2 ○Yukuto Yasuhiko1, Satoshi Kitajima1, Yu Takahashi1, Masayuki Oginuma2, Harumi Kagiwada3, Jun Kanno1, Yumiko Saga2 (NIHS1, NIG2, RICE-AIST3) | |
| W1-04: 13:55-14:10 | Emergence of coordinated oscillation in the segmentation clock ○Kana Ishimatu, Daisuke Shirakawa, Yutaro Kii, Hiroyuki Takeda (Dept. Biol. Sci, Univ. Tokyo) | |
| W1-05: 14:10-14:25 | Secondary neurulation: a novel model to study tubulogenesis ○Eisuke Shimokita, Itsuki Kashin, Yoshiko Takahashi (NAIST) | |
| W1-06: 14:25-14:40 | Imaging analysis of the apical structure of neuroepithelial cells: evidence for hindbrain cytonemes ○Masanori Takahashi1, Noriko Osumi1,2 (Div.of Dev.Neurosci., Tohoku Univ.Grad.Sch.of Med.1, CREST, JST2) | |
| W1-07: 14:40-14:55 | Unidirectional sensitivity exists at the PFR to specify digit identity through unique level of SMAD1/5/8 activity ○Takayuki Suzuki1,2, Sean M. Hasso2, John F. Fallon2, Ogura Toshihiko1 (IDAC1, UW-Madison, USA2) | |
| W1-08: 14:55-15:10 | Spatiotemporal patterns of caspase activation during Drosophila abdominal epithelial morphogenesis revealed by in vivo imaging analysis ○Yuichiro Nakajima1, Erina Kuranaga1,2, Masayuki Miura1,2 (Grad.Sch.Pharmaceutical Sci.,Univ.Tokyo1, CREST, JST2) | |
| W1-09: 15:15-15:30 | Dorsal determination by a maternal factor Tokkaebi/Syntabulin in zebrafish ○Hideaki Nojima, Masahiko Hibi (RIKEN CDB) | |
| W1-10: 15:30-15:45 | Prickle1, a mouse homolog of a Drosophila PCP gene, is essential for the establishment of epiblast polarity during early development ○Hirotaka Tao1, Takaya Abe2, Hiroshi Kiyonari2, Naoto Ueno1 (Div. for Morphogenesis, NIBB1, LARGE, RIKEN2) | |
| W1-11: 15:45-16:00 | Nonmuscle Myosin II heavy chain, Zipper is required for the left-right asymmetric morphology of the anterior midgut in Drosophila embryo ○Takashi Okumura, Hiroo Fujiwara, Kiichiro Taniguchi, Reo Maeda, Syunya Hozumi, Naotaka Nakazawa, Mitsutoshi Nakamura, Haruka Yamamoto, Kenji Matsuno (Dept. Biol. Sci./Tec., Tokyo Univ of Sci.,) | |
| W1-12: 16:00-16:15 | Transition of Sox2 gene regulation distinguishes epiblastic and anterior neural plate states ○Makiko Iwafuchi, Tatsuya Takemoto, Masanori Uchikawa, Yusuke Kamachi, Hisato Kondoh (Dev.Biol.Gr., Grad.Sch.of Frontier Bioscis., Osaka Univ.) | |
| W1-13: 16:15-16:30 | Functional redundancy of Tcf7 and Lef1, transcription factors mediating the Wnt signaling pathway, during zebrafish fin development ○Gembu Abe, Saori Nagayoshi, Koichi Kawakami (Mol. Dev. Biol., NIG) | |
| W1-14: 16:30-16:45 | Xenopus ONT1 is a novel secreted pro-BMP factor that restricts Chordin in axial development ○Hidehiko Inomata, Tomoko Haraguchi, Yoshiki Sasai (CDB) | |
| W1-15: 16:45-17:00 | Secreted Frizzled-related proteins, Frzb1 and Crescent, alter diffusivity of Wnt ligands through extracellular interactions. ○Yusuke Mii, Masanori Taira (Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Univ. of Tokyo) | |
| W1-16: 17:00-17:15 | Maintenance of genomic methylation during preimplantation development is regulated by the somatic form of DNA methyltransferase 1 ○Yukiko Kurihara1, Yumiko Kawamura1, Yasunobu Uchijima1, Hiroshi Kobayasi1, Tomoichiro Asano2, Hiroki Kurihara1 (Univ. of Tokyo1, Hiroshima univ.2) | |
| Workshop 2: Organogenesis |
| Organizer: Shigeo Hayashi (CDB, RIKEN) |
| Room: B |
| W2-01: 13:10-13:25 | Microtubule-dependent targeting of E-cadherin in de novo adherence junction formation during epithelial organogenesis ○Kagayaki Kato1, Housei Wada1, Shigeo Hayashi1,2 (RIKEN CDB1, Dept. biol., Kobe Univ. Grad. School of Sci.2) | |
| W2-02: 13:25-13:40 | Analyses of master genes for insect wing development, vestigial and scalloped, in the water flea, Daphnia magna (Crustacea, Cladocera) ○Yasuhiro Shiga, Yuko Aragane, Takayuki Haraguchi, Hideo Yamagata (Tokyo Univ. Pham. & Life Sci., Sch.of Life Scis.) | |
| W2-03: 13:40-13:55 | Xenopus laevis DM-W on the W-chromosome causes female-specific expression of Foxl2 and aromatase genes in primary ovary formation ○Shin Yoshimoto1, Ema Okada1, Hiromi Kanda1, Kei Tamura1, Yoshinobu Uno2, Chizuko Nishida-Umehara2, Yoichi Matsuda2, Tadayoshi Shiba1, Nobuhiko Takamatsu1, Michihiko Ito1 (Dept. Biosci., Sch. Sci., Kitasato Univ.1, Division of Genome Dynamics, Creative Research Initiative “Sousei”, Hokkaido University2) | |
| W2-04: 13:55-14:10 | Imaging by high resolution phase contrast X-ray computed micro-tomography reveals 3D structures of developing teeth and brain in zebrafish and medaka Tamami Yamamoto1, Keisuke Yoshida2, Takuto Hashimoto2, Yasushi Kagoshima2, Kentaro Uesugi3, Akihisa Takeuchi3, Yoshio Suzuki3, Mariko Itoh1, Erika Isoda1, Moly PRICILA KHAN1, ○Kohei Hatta1 (Life Sci, U of Hyogo1, Material Sci, U of Hyogo2, JASRI3) | |
| W2-05: 14:10-14:25 | Skeletal muscle development in zebrafish ○Haruki Ochi1,2, Monte Westerfield2 (NAIST1, Institute of Neuroscience, University of Oregon2) | |
| W2-06: 14:25-14:40 | Characterization of the medaka mutant which displays abnormalities in vertebral body ○Satoshi Ohisa1, Keiji Inohaya, , and1, Atsushi Kawakami1, Yoshiro Takano2, Akira Kudo1 (Tokyo, Inst, Tech1, Section of Biostructural Science, Tokyo Medical and Dental University Graduate School, Tokyo, Japan2) | |
| W2-07: 14:40-14:55 | Role of mouse Shh in the prechordal mesendoderm cells during midline specification Kazushi Aoto1, Yayoi Shikata1, Daisuke Matsumaru2, Gen Yamada2, ○Jun Motoyama1 (RIKEN BSI1, CARD, Kumamoto-univ2) | |
| W2-08: 14:55-15:10 | Chromatin remodeling factors in cardiogenesis ○Jun Takeuchi1, Kauzko Koshiba1, Benoit Bruneau2 (GE, Tokyo-Tech1, Cardivascular Disease of Gladstone Institute and UCSF2) | |
| Workshop 3: Neural development & behaviour and neural circuit development | |
| Organizers: | Testsuya Tabata (University of Tokyo), |
| Hitoshi Okamoto (RIKEN Brain Science Institute) | |
| Room: B | |
| W3-01: 15:15-15:30 | Role of holm/mosaic eyes, a Neuroepithelial Polarity Gene in the Migration of Vagus Motor Neuron Precursors ○Shinya Ohata1, Kinoshita Shigeharu1, Tsuruoka Sachiko1, Tanaka Hideomi1, Wada Hironori1, Masai Ichiro2, Okamoto Hitoshi1 (Lab. for Developmental Gene Regulation, BSI, RIKEN1, Developmental Neurobiology Unit, OIST2) | |
| W3-02: 15:30-15:45 | Regulation of neurogenesis by zinc-finger genes Fezf1 and Fezf2 in forebrain Masato Nakazawa1, Shimizu Takeshi1, Tsutomu Hirata1, YOUNG-KI Bae1, Takashi Shimizu1, Ryoichiro Kageyama2, ○Masahiko Hibi1 (RIKEN CDB1, Institute for Virus Research, Kyoto Univ.2) | |
| W3-03: 15:45-16:00 | Tbx10 is a useful marker for superior salivatory neurons ○Xiaodong Xue, Keisuke Hikosaka, Wataru Kimura, Naoyuki Miura (HUSM) | |
| W3-04: 16:00-16:15 | Knot/Collier and Cut Control Different Aspects of Dendrite Cytoskeleton and Synergize to Define Final Arbor Shape Shiho Jinushi-Nakao, Ramanathan Arvind, Reiko Amikura, Emi Kinameri, Andrew Liu, ○Adrian Moore (RIKEN BSI) | |
| W3-05: 16:15-16:30 | Developmental changes of nervous system during metamorphosis in the ascidian Ciona intestinalis ○Takeo Horie1, Nori Satoh2, Yasunori Sasakura1 (Shimoda Marine Research Center, University of Tsukuba1, Department of Zoology, Graduate School of Science, Kyoto University,2) | |
| W3-06: 16:30-16:45 | Drosophila optic lobe neuroblasts triggered by a wave of proneural gene expression that is negatively regulated by JAK/STAT ○Tetsuo Yasugi, Daiki Umetsu, Satoshi Murakami, Sato Makoto, Tetsuya Tabata (IMCB, Univ. Tokyo) | |
| W3-07: 16:45-17:00 | Cadherins and vocal learning in songbird ○Eiji Matsunaga, Kazuo Okanoya (Lab for Biolinguistics, RIKEN BSI) | |
| W3-08: 17:00-17:15 | Molecular relationship among the responsible genes for ocular malformation ○Hiroki Danno1, Tatsuo Michiue2, Keisuke Hitachi1, Akira Yukita1, Shoichi Ishiura1, Makoto Asashima1,2,3 (Univ. of Tokyo1, AIST2, JST3) | |
| Workshop 4: Signalling in development |
| Organizers: Masanori Taira (University of Tokyo), Motoyuki Itoh (Nagoya University) |
| Room: C |
| W4-01: 13:10-13:25 | Characterization of the Wnt cis-element in the cnidarian Hydra and insight into the origin of axis patterning system. ○Yukio Nakamura, Thomas Holstein (Dept. of Molecular Evolution and Genomics, Heidelberg Inst. of Zoology, Univ. of Heidelberg) | |
| W4-02: 13:25-13:40 | GPCR kinase regulates spatiotemporal pattern of cell movements during Drosophila gastrulation. ○Naoyuki Fuse, Susumu Hirose (NIG) | |
| W4-03: 13:40-13:55 | Jagged-Notch signaling is involved in zebrafish notochord development Mai Yamamoto1, Kunihiro Matsumoto2, Shigenomu Yonemura3, Koichi Kawakami4, ○Motoyuki Itoh1 (IAR, Nagoya Univ,1, Div.Biol.Sci,, Grad. Sch. Sci., Nagoya Univ,2, RIKEN, CDB3, NIG4) | |
| W4-04: 13:55-14:10 | Nemo-like kinase is a critical mediator of NGF-regulated axonal development ○Tohru Ishitani1, Shizuka Ishitani1, Kunihiro Matsumoto2 (Div. of Cell Reg. Sys., Med. Ins. of Bioreg., Kyushu Univ.1, Lab. of Cell Reg., Div. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Nagoya Univ.2) | |
| W4-05: 14:10-14:25 | Functional analysis of the RNA binding protein RKHD3 and its 3’ long conserved untranslated region in Xenopus neural development ○Hitomi Takada1, Hiroshi Mamada1, Yuzuru Ito2, Reiko Kikuno3, Hisashi Koga3, Makoto Asashima2, Masanori Taira1 (Dept. of Biol. Sci, Univ. of Tokyo1, Dept. of Life Sci, Univ. of Tokyo and ICORP, AIST2, Kazusa DNA institute3) | |
| W4-06: 14:25-14:40 | Semaphorin controls epidermal morphogenesis by stimulating mRNA translation via eIF2α in C. elegans ○Akira Nukazuka, Hajime Fujisawa, Toshifumi Inada, Yoichi Oda, Shin Takagi (Nagoya Univ.) | |
| W4-07: 14:40-14:55 | The role of Shh signaling and FGFs in the mouse molar tooth root development ○Masato Ota, Shigeru Okuhara, Sachiko Iseki (TMDU, Grad.Sch., Mol.Craniofacial Emb.) | |
| W4-08: 14:55-15:10 | Downstream of FGF signaling in the development of mouse lacrimal gland ○Masataka Ito1, Yoshiaki Ueda2, Yoko Karasawa2, Yoko Kameda3, Junko Imaki1, Noriko Gotoh4 (Dept. of Develop. Anatomy, NDMC1, Dept. of Ophthalmol., NDMC2, Dept. of Anatomy, Kitasato Univ.3, Div. of Systems Biomed. Technol., IMSUT4) | |
| Workshop 5: Cell biology of development (growth control,adhesion,migration) | |
| Organizers: | Fumio Matsuzaki (CDB RIKEN), |
| Leo Tsuda (National Institute for Longevity Sciences) | |
| Room: C | |
| W5-01: 15:15-15:30 | Functional analysis of a novel zebrafish mutant that has defects in the migration of myocardial precursor cells ○Atsuo Kawahara1,2, Naoki Mochizuki1 (NCVC Japan1, HMRO Kyoto Univ. Japan2) | |
| W5-02: 15:30-15:45 | The mechanisms of subcellular localization of CyclinD2 mRNA and the protein in the mouse brain primodium ○Yuji Tsunekawa1, Masanori Takahashi1, Noriko Osumi1,2 (Dept.of Dev.Neurobiol., Tohoku Univ.Grad.Sch.of Med.1, CREST, JST2) | |
| W5-03: 15:45-16:00 | Dissecting cell competition through a non-cell autonomous genetic screen ○Tatsushi Igaki1, Tian Xu2 (Kobe Univ. Grad. Sch. of Med.1, Yale Univ. Sch. of Med.2) | |
| W5-04: 16:00-16:15 | In vivo and In vitro analyses of neural crest migration ○Sei Kuriyama1, Helen Matthews1, Lorena Marchant1, Carlos CARMONA-FONTAINE1, Juan Larrain2, Mark Holt3, Maddy Parsons3, Roberto Mayor1 (UCL1, UC2, KCL3) | |
| W5-05: 16:15-16:30 | Nuclear localization of PTEN is involved in cell cycle elongation after MBT in Xenopus embryos ○Shuichi Ueno, Yasuhiro Iwao (Mol. Dev. Biol.,Applied Mol. BioSci.,Yamaguchi Univ.) | |
| W5-06: 16:30-16:45 | FoxM1-driven cell division is required for neuronal differentiation in early Xenopus embryos ○Hiroyuki Ueno1, Nobushige Nakajo1, Minoru Watanabe2, Michitaka Isoda1, Noriyuki Sagata1 (Department of Biology, Graduate School of Sciences, Kyushu University1, Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima2) | |
| W5-07: 16:45-17:00 | Comprehensive analysis of the interkinetic nuclear migration in developing mouse brain ○Yoichi Kosodo1, Akatsuki Kimura2, Taeko Suetsugu1, SHOJI A. Baba3, Fumio Matsuzaki1 (RIKEN CDB1, NIG2, Ochanomizu Univ.3) | |
| W5-08: 17:00-17:15 | Laminin regulates the interkinetic nuclear migration in neuroepithelial cells ○Sachiko Tsuda, Takeda Hiroyuki (Grad. School of Science, Dep. of Biological Sciences, Univ. of Tokyo) | |
| 30 May, 13:10 - 15:10 |
| Workshop 6: Reproduction & gametology | |
| Organizers: Gen Yamada (Kumamoto University), Yoshiakira Kanai (University of Tokyo) | |
| Room: A | |
| W6-00: 13:10-13:15 | Foreword Gen Yamada (Kumamoto University, CARD) | |
| W6-01: 13:15-13:40 | Urothelial trans-differentiation to prostate epithelia is mediated by paracrine TGF-ß signaling Xiaohong Li, Simon W. Hayward, ○Neil A. Bhowmick (Department of Urologic Surgery, Vanderbilt University Nashville TN, USA) | |
| W6-02: 13:40-14:05 | Function of androgen receptor in prostate cancer development ○Shigeaki Kato1,2 (Institute of Molecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo1, ERATO, Japan Science and Technology Agency2) | |
| W6-03: 14:05-14:25 | Potentiality of creating gametes from ES cells in culture ○Toshiaki Nose (MITILS) | |
| W6-04: 14:25-14:45 | Abnormal epithelial cell polarity and migration of Emx2 KO embryonic gonads induced by ectopic EGFR expression Masatomo Kusaka, ○Yuko Katoh-Fukui, Hidesato Ogawa, Kanako Miyabayashi, Takashi Baba, Noriyuki Sugiyama, Yukihiko Sugimoto, Yasushi Okuno, Ryuji Kodama, Akiko Iizuka-Kogo, Takao Senda, Shinichi Aizawa, Ken-ichirou Morohashi (Division for sex differentiation, National institute for Basic Biology, National Institutes of Natural Sciences) | |
| W6-05: 14:45-15:05 | A critical time window of Sry action in gonadal sex determination Ryuji Hiramatsu, Shogo Matoba, ○Yoshiakira Kanai (Vet Anat, Univ.of Tokyo) | |
| W6-06: 15:05-15:10 | Concluding remark Yoshiakira Kanai (University of Tokyo) | |
| Workshop 7: Evolution and development | |
| Organizer: Kenji MATSUNO (Tokyo University of Science) | |
| Room: B | |
| W7-01: 13:10-13:25 | Radiata evolved from Bilateria? : Directed locomotion of sea anemone ○Hiroshi Shimizu1, Setsuro Kobayashi2, Hiroshi Namikawa3 (NIG1, Mishima Kita High School2, Showa Memorial Institute, National Museum of Nature and Science3) | |
| W7-02: 13:25-13:40 | Protein evolution of the LIM-homeodomain transcription factors Lhx1 and Lhx3 in acquisition of the vertebrate gastrula organizer ○Yuuri Yasuoka1, Masaaki Kobayashi2, Daisuke Kurokawa3, Koji Akasaka3, Hidetoshi Saiga2, Masanori Taira1 (Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Univ. of Tokyo1, Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Tokyo Metropolitan Univ.2, MMBS, Grad. Sch. of Sci., Univ. of Tokyo3) | |
| W7-03: 13:40-13:55 | Molecular analysis of morphogenesis of segmented structure in feather stars (echinoderm) ○TOMOKO F. Shibata1, Yumiko Saga2, Koji Akasaka1 (MMBS, Tokyo Univ.1, National Institute of Genetics2) | |
| W7-04: 13:55-14:10 | Chordin, Dkk3 and Hex are required for the forebrain development in Amphioxus embryos. ○Takayuki Onai1, Ira Blitz2, Ken W Cho2, Linda Z Holland1 (UCSD1, UCI2) | |
| W7-05: 14:10-14:25 | Distinct modifications of EGF receptor signaling in the homoplastic evolution of eggshell morphology in genus Drosophila. ○Tatsuo Kagesawa, Yukio Nakamura, Minori Nishikawa, Kenji Matsuno (Dept.of Biol.Sci.& Technol., Tokyo Univ.of Sci.) | |
| W7-06: 14:25-14:40 | Evolutionary developmental (evo-devo) study of the mammalian middle ear ○Masaki Takechi, Shigeru Kuratani (RIKEN CDB) | |
| W7-07: 14:40-14:55 | Comparative genomic analysis of the cellular slime moulds to reveal how cell differentiation was established during evolution ○Hidekazu Kuwayama1, Ryuji Yoshino1, Hiroshi Kagoshima2, Tadasu SHIN-I2, Kazuko Oishi2, Takehiko Itoh3, Takeaki Taniguchi3, Kyoko Uchi1, Yoko Kuroki4, Yuji Kohara4, Asao Fujiyama5, Hideko Urushihara1 (Univ. of Tsukuba , Life and Environmental Scicences1, Nat. Inst. Genet.2, Mitsubishi Res. Inst.3, RIKEN Yokohama Inst.4, Nat. Inst. Info.5) | |
| W7-08: 14:55-15:10 | Towards a pan-genome atlas of transcription factor DNA-binding specificity in Ciona intestinalis Renaud Vincentelli2,4, ○Kazuhiro Nitta1,4, Agnes Mistral2, Atsushi Kubo3, Yutaka Satou3, Christian Cambillau2, Patrick Lemaire1 (IBDML-UMR 62161, AFMB-UMR CNRS 60982, Zoology department, Graduate School of Science, Kyoto Universtity3, Equal contributors4) | |
| Workshop 8: Stem cells and pluripotency, regeneration | |
| Organizers: Shoen Kume (Kumamoto University), Kunimasa Ohota (Kumamoto University) | |
| Room: C | |
| W8-01: 13:10-13:25 | Tsukushi is a Frizzled4 ligand that, in competition with Wnt2b, regulates the proliferation of retinal stem/progenitor cells ○Kunimasa Ohta1, Ayako Ito1,2, Sei Kuriyama1, Rika Nakayama3, Naoko Oshima3, Mitsuko Kosaka3, Shinichi Ohnuma4, Shinichi Nakagawa5, Hideaki Tanaka1,2 (Dept.of Dev.Neurobiol., Kumamoto Univ.Grad.Sch.of Med.Scis.1, Kumamoto Univ., Global COE, Kumamoto, Japan2, RIKEN CDB, Kobe, Japan3, Univ. of Cambridge, Cambridge, UK4, RIKEN FRS, Wako, Japan5) | |
| W8-02: 13:25-13:40 | Reactivation of SHH signaling is a key to anterior-posterior (AP) repatterning during Xenopus froglet limb regeneration ○Nayuta Yakushiji1, Tomoko Sagai2, Toshihiko Shiroishi2, Hisato Kobayashi3,4, Hiroyuki Sasaki3,4, Hiroyuki Ide1, Koji Tamura1 (Grad.Life Sci.,Tohoku Univ1, Mammalian Genetics Laboratory, Nat'l Inst. of Genetics2, Division of Human Genetics, Nat'l Inst. of Genetics3, SOKENDAI4) | |
| W8-03: 13:40-13:55 | Gene Expression and Functional Analysis of Zebrafish Larval Fin-Fold Regeneration Takashi Ishida, Nozomi Yoshinari, Akira Kudo, ○Atsushi Kawakami (Tokyo Tech.) | |
| W8-04: 13:55-14:10 | Guided differentiation of ES cells into Pdx1-expressing regional specific definitive endoderm ○Nobuaki Shiraki1, Tetsu Yoshida1, Kimi Araki2, Akihiro Umezawa3, Yuichiro Higuchi1, Hideo Goto1, Kazuhiko Kume1, Shoen Kume1 (Div. of Stem Cell Biol. IMEG, Kumamoto Univ.1, Div. Developmental Genetics, IMEG, Kumamoto Univ.2, Natl. Inst. Child Health Dev,. Rep. Biol.3) | |
| W8-05: 14:10-14:25 | Mechanism of differentiation of skeletal muscle into fast and slow muscles Yoshikazu Matsoka, ○Akio Inoue (Dept. Biol. Grad. Sch. Dci. Osaka Univ.) | |
| W8-06: 14:25-14:40 | Specification of fusion-competent areas of plasma membrane in myogenic cells Atsushi Mukai, ○Naohiro Hashimoto (Dept Reg Med, NISL, NCGG) | |
| W8-07: 14:40-14:55 | Inhibition of myogenesis and myogenin promoter activity by mutated ALK2 found in a heritable human disease ○Michiko Yanagisawa, Naohiro Hashimoto (Dept Reg Med, NILS, NCGG) | |
| Poster presentations |
| 28 May, 09:00 - 19:15 & 29 may, 09:00 - 12:00, Exhibition Room |
| Poster 1 : | Discussion time: 28 May | 17:15 - 18:15 for even No. posters. 18:15 - 19:15 for odd No. posters. |
| 1P001: | PI3K/TOR pathway is involved in cell cycle elongation during Xenopus early embryogenesis ○Tomoyo Takimizu, Shuichi Ueno, Yasuhiro Iwao (Mol. Dev. Biol., Applied Mol. BioSci., Yamaguchi Univ.) | |
| 1P002: | Function of actin-binding protein FIlaminB in developing neural epithelium ○Yoshio Wakamatsu1, Daisuke Sakai2, Takashi Suzuki3, Noriko Osumi3 (Dept.of Dev.Neurobiol., Tohoku Univ.Grad.Sch.of Med.1, Stowers Inst. Med. Res.2, Div. of Dev. Neurosci., CTAAR, Tohoku Univ. Grad. Sch. of Med.3) | |
| 1P003: | Expression and function of ATF4 in the epithelial-mesenchymal transition of neural crest cells ○Takashi Suzuki, Noriko Osumi, Yoshio Wakamastu (Div. of Dev. Neurosci., Grad. Sch. of Med., Tohoku Univ.) | |
| 1P004: | Downregulation of ninein, δ-catenin and FEZ1 at the apical side of neuroepithelial cells of the Pax6 mutant ○Hiroshi Shinohara1, Kensuke Hayashi2, Takaki Miyata3, Masanori Takahashi1, Noriko Osumi1 (Div. Dev. Neurosci., Tohoku Univ. Sch. Med.1, Life Sci. Inst., Sophia Univ.2, Dep. Anat. Cell Biol Grad. Sch. Med. Nagoya Univ.3) | |
| 1P005: | Up-regulated genes at embryonic diapause termination in cysts of crustacean Artemia franciscana ○Shin Tanaka, Fumiko Nambu, Ziro Nambu (UOEH) | |
| 1P006: | Pair-generated “infantile” daughter cells asymmetrically activate the neocortical Ngn2-Tbr2 cascade ○Sayaka Nakatani1, Wataru Ochiai1, Taishi Takahara1, Masahiko Kainuma1, Makoto Masaoka1, Masakazu Namihira2, Kin-ichi Nakasima2, Masaharu Ogawa3, Takaki Miyata1,3 (Anat and Cell Biol, Nagoya Univ Grad Sch Med1, Mol Neurosci, Grad Sch Biol Sci, NAIST2, Cell Cul Dev, BSI, RIKEN3) | |
| 1P007: | Identification and characterization of obif, a novel transmembrane protein, promotes osteoblast differentiation. ○Takashi Kanamoto1,2, Hideki Yoshikawa2, Takahisa Furukawa1 (Dept. of Dev. Biol., OBI1, Dept. of Orthop. Surg., Osaka Univ.2) | |
| 1P008: | Analysis of the novel Patched functions through the generation of its cytoplasmic fragment ○Hiroki Kagawa1, Masumi Shimada2, Hiroyuki Kawahara2 (Grad. Sch. Pharm. Sci., Hokkaido Univ.1, Dept. Biochem., Tokyo Metropol. Univ.2) | |
| 1P009: | Isolation and Culture of Rabbit Primordial Germ Cells ○Ryo Kakegawa1, Toshiyuki Takehara1, Takeshi Teramura2, Naoto Fukunaga3, Syunsuke Ito3, Yuki Miyamoto3, Yoshiko Tujimoto3, Satosi Kisigami3, Kazuya Matsumoto3, Kazuhiro Saeki3, Akira Iritani3, Norimasa Sagawa2, Yoshihiko Hosoi3 (Grad. Sch. B.O.S.T. Kinki Univ.1, Dep. Obs. Gynec. Grad. Sch. Med. Mie univ.2, Dep. B.O.S.T. Kinki Univ.3) | |
| 1P010: | Analysis of molecular mechanism for the craniofacial abnormalities in Nax mouse ○Minoru Kawakami1, Naomi Nakagata2, KEN-ICHI Yamamura1 (Kumamoto Univ. IMEG1, Kumamoto Univ. CARD2) | |
| 1P011: | Xtr, One of The Key Proteins for Progression of Meiotic Cycle in Xenopus laevis ○Hiroki Ohgami1, Masateru Hiyoshi2, Hideo Kubo3, Sin-Ichi Abe1, Kazufumi Takamune1 (GSST-Kumamoto1, Division of Hematopoiesis, Center for AIDS Research, Kumamoto University2, Department of Medical Biology, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science3) | |
| 1P012: | A genetic screen to identify genes involved in the left-right asymmetric development of the gut in Drosophila embryo ○Naotaka Nakazawa, Kiichiro Taniguchi, Takashi Okumura, Reo Maeda, Shunya Hozumi, Mitsutoshi Nakamura, Haruka Yamamoto, Takeshi Kusama, Ryo Hatori, Kenji Matsuno (Dept.Biol.Sci/Tec,Tokyo Univ.Sci) | |
| 1P013: | Characterization of ectodermal layer formation in Cynops pyrrhogaster embryo ○Hiromasa Ninomiya, Rudolf Winklbauer (Univ. of Toronto, CSB) | |
| 1P014: | A role of the adherens junction in neural cell fate regulation ○Jun Hatakeyama, Kenji Shimamura (IMEG, Kumamoto Univ.) | |
| 1P015: | Regulation for neural tube morphogenesis by necitn, an Ig-like adhesion molecule ○Hitoshi Morita1,2, Chie Terasaka1, Takamasa S. Yamamoto1, Naoto Ueno1,2 (NIBB1, SOKENDAI2) | |
| 1P016: | Infrared laser mediated gene induction in a single cell of C. elegans ○Motoshi Suzuki1, Yasuhiro Kamei2, Yoichi Oda1, Shunsuke YUBA 3, Shin Takagi1 (Nagoya University1, Dept of Radiation Biology and Medical Genetics, Graduate School of Medicine, Osaka University2, National Institute of Advanced and industrial Science and Technology3) | |
| 1P017: | Functional analysis of Kintoun, a novel cytoplasmic protein required for the motility of cilia/flagella ○Moe Matsuo1, Akira Sumeragi1, Tatsuya Tsukahara1, Daisuke Kobayashi2, Toshiki Yagi3, Yumiko Saga4, Ritsu Kamiya1, Hiroyuki Takeda1, Sumito Koshida1 (Grad. School of Sci., The Univ. of Tokyo1, Department of Anatomy and Developmental Biology, Kyoto Prefecture University of Medicine, Graduate School of Medical Science2, Department of Biophysics, Division of Biological Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University3, Division of Mammalian Development, National Institute of Genetics, and Department of Genetics4) | |
| 1P018: | A genetic screen to identify the genes regulating γ-Secretase activities in Drosophila melanogaster ○Naoki Aoyama1, Misako Sasaki1, Yuka Yoshida1, Toshiro Aigaki2, Kenji Matsuno1 (TUS1, Tokyo Met.Univ.2) | |
| 1P019: | Elastic analysis of the tissue growth in Drosophila ○Kaoru Sugimura1, Shuji Ishihara2, Tadashi Uemura3, Atsushi Miyawaki1 (RIKEN BSI1, Univ. Tokyo2, Kyoto Univ.3) | |
| 1P020: | A DNA Chip analysis of a biological timer in the oligodendrocyte development ○Yasuhito Tokumoto, Shinichiro Ogawa, Teruyuki Nagamune, Jun Miyake (Dep. Bioengineering, Univ. Tokyo) | |
| 1P021: | The endocytic pathway regulates the Oskar-mediated F-actin reorganization during Drosophila germ plasm assembly ○Tsubasa Tanaka, Akira Nakamura (RIKEN CDB) | |
| 1P022: | Cell context dependent Sonic hedgehog signaling ○Vincent CH Lui, Tracy HC Poon, Elly SW Ngan, Paul KH Tam (HKU) | |
| 1P023: | Redundant roles of Tead1 and Tead2 in notochord development and the regulation of cell proliferation and survival ○Mitsunori Ota, Atsushi Sawada, Hiroshi Kiyonari, Kanako Ukita, Noriyuki Nishioka, Yu Imuta, Hiroshi Sasaki (RIKEN CDB) | |
| 1P024: | KEGG PATHWAY analysis of the EGTC clones. ○Masatake Araki1, Kumiko Yoshinobu1, Kyoko Haruna2,3, Yumi Sakumura2,3, KEN-ICHI Yamamura2,3, Kimi Araki3 (Div. of Bioinformatics, IRDA, Kumamoto Univ.1, Division of Developmental Genetics, Institute of Molecular Embryology and Genetics, Kumamoto University2, TransGenic Inc.3) | |
| 1P025: | New microscope enabling 3D live imaging of embryos ○Takehiko Ichikawa1, Philipp Keller2, Ernst Stelzer2, Shigenori Nonaka1 (NIBB1, EMBL2) | |
| 1P026: | Utilization of fluid from eye sacs of Bubble-Eye Goldfish (Carassius auratus) ○Etsuko Sawatari1, Tomoko Adachi1, Hisashi Hashimoto1, Takaharu Matsumura2, Yasuhiro Iwata2, Naoki Yamamoto2, Yuko Wakamatsu1 (Biosci. Biotech. Ctr. Nagoya Univ.1, Yatomi St. Aichi Fish. Res. Inst.2) | |
| 1P027: | A nuclear factor, ebi, inhibits G1-S transition by regulating E2F activity during photoreceptor cells development in Drosophila ○Leo Tsuda, Young-Mi Lim (NILS) | |
| 1P028: | Functional analysis of Sox2 in differentiation of extra-embryonic endoderm lineages ○Satsuki Fukuda1, Satoko Yoshitake2, Kiyoko Nashiro2, Tatsuo Hamazaki2, Hitoshi Okochi2, Shinji Masui1 (Division of Molecular Biology and Cell Engineering, Department of Regenerative Medicine, International Medical Center of Japan1, Department of Regenerative Medicine, International Medical Center of Japan2) | |
| 1P029: | Epithelial tube morphogenesis – Formation of a fine tube of single cell-size circumference ○Hisao Honda1, Tatsuzo Nagai2 (Health Sci. Hyogo Univ.1, Kyushu Kyoritu Univ.2) | |
| 1P030: | Visualization of the segmentation clock by real-time imaging of Hes7 expression ○Yoshiki Takashima1,2, Yoshito Masamizu1, Toshiyuki Ohtsuka1, Yamada Shuichi3, Kageyama Ryoichiro1 (Inst. Virus Res., Kyoto Univ.1, Kyoto Univ. Grad. Stu. Biostudies2, Biosci. Res.-Edu. Ctr., Akita Univ.3) | |
| 1P031: | Shaping cells and ECM into ball-and-socket joints in the fly leg: roles of Notch signaling ○Reiko Tajiri, Shigeo Hayashi (RIKEN CDB) | |
| 1P032: | Determination of dorsal-ventral polarity within the optic vesicle by Shh and FGF8 signals. ○Takuma Kobayashi1,2, Yoshiko Takahashi1, Masasuke Araki2 (NAIST1, Developmental Neurobiology Laboratory, Faculty of Science, Nara Women’s University2) | |
| 1P033: | Regulatory mechanisms for the expression of Hox genes in mouse neural crest cells ○Shinkichi Ishikawa, Kazuo Ito (Dept. of Biol. Sci., Grad. Sh. of Sci., Osaka Univ.) | |
| 1P034: | Cellular image profiling of neural differentiation pattern of mouse embryonic stem cells with morphological information ○Reiko Nagano1, Shigeru Koikegami2, Satoshi Imanishi1, Seiichiroh Ohsako3, Hiroko Zaha1, Masahiro Okura1, Junzo Yonemoto1, Hideko Sone1 (NIES1, Secound Lab, LLC2, CDBIM, The University of Tokyo3) | |
| 1P035: | PETA3 is a novel Wnt/PCP pathway component in zebrafish ○Yasuyuki Kida, Kota Miyasaka, Mari Minami, Toshihiko Ogura (IDAC) | |
| 1P036: | Identification and characterization of a novel candidate gene that regulates competence of ectodermal cells to BMP-mediated embryonic induction ○Tatsuo Miyamoto, Tomoko Nagata, Kimiko TAKEBAYASHI-SUZUKI, Atsushi Suzuki (Inst. Amphibian Biol., Grad.Sch. of Sci., Hiroshima Univ.) | |
| 1P037: | Shroom3 regulates neuroepithelial cell rearrangement during neural tube closure by recruiting ROCKs to the apical junctions ○Tamako Nishimura, Masatoshi Takeichi (RIKEN CDB) | |
| 1P038: | Expression patterns of Ror2 receptor tyrosine kinase in mouse gut development ○Makiko Yamada1, Mayumi Hamasaki2, Jun Udagawa1, Akihiro Matsumoto1, Ryuju Hashimoto1, Michiru Nishita2, Yasuhiro Minami2, Hiroki Otani1 (Dept Developmental Biology, Fac Med, Shimane Univ1, Div Cell Physiology, Dept Physiology and Cell Biology, Kobe Univ Grad Sch Med2) | |
| 1P039: | Mesp2 and Tbx6 cooperatively create periodic patterns, coupled with the clock machinery during mouse somitogenesis ○Masayuki Oginuma1, Niwa Yasutaka2, Chapman Deborah L3, Saga Yumiko4 (SOKENDAI1, Institute for Virus Research, Kyoto University2, Department of Biological Sciences, University of Pittsburgh3, Div.of Mammalian Development, Nat'l Inst.of Genetics4) | |
| 1P040: | BMP antagonism is required in both the node and lateral plate mesoderm for mammalian left-right axis establishment ○Naoki Mine, John Klingensmith (DUKE UNIVERSITY) | |
| 1P041: | Modeling of the Hes7 regulation by the Fgf and Notch pathways during the mouse somitogenesis ○Aitor Gonzalez, Ryoichiro Kageyama (IVR) | |
| 1P042: | Neptune is required for neural crest development in Xenopus ○Takayuki Kurauchi1, Yumi Izutsu2, Mitsugu Maeno2 (Graduate School of Science and Technology, Niigata University1, Department of Biology, Faculty of Science, Niigata University2) | |
| 1P043: | Genetic evidence for the Mesp2 function as the suppressor of Notch signaling ○Nobuo Sasaki, Makoto Kiso, Yumiko Saga (NIG, Dept. of Mammalian Development) | |
| 1P044: | Hunting for novel genes that regulate planar cell polarity ○Kousuke Mouri1, Shin-ya Horiuchi1, Toshiyuki Harumoto1, Yuko Shimada1, Gohta Goshima2, Tadashi Uemura1 (Grad. Sch. of Biostudies , Kyoto Univ.1, IAR, Nagoya Univ.2) | |
| 1P045: | Microtubule-associated RING finger proteins regulate neural tube closure in Xenopus embryo ○Makoto Suzuki1,2, Naoto Ueno1 (NIBB1, JSPS Research Fellow2) | |
| 1P046: | Moderate suppression of BMP signaling is sufficient for Nodal expression during the left-right axis formation in chick embryo ○Kenjiro Katsu, Yuji Yokouchi (IMEG, Kumamoto Univ.) | |
| 1P047: | Beta1,4-galactosyltransferase 2 is required for convergence and extension movements during medaka (Oryzias latipes) gastrulation ○Yasuhiro Tonoyama1, Daisuke Anzai2, Atsushi Ikeda2, Shinako Kakuda1, Masato Kinoshita3, Toshisuke Kawasaki4, Shogo Oka1 (Dept. Biochem, Health Sci. Grad. Sch. Med., Kyoto Univ.1, Dept. Biochem. Grad. Sch. Pharm., Kyoto Univ.2, Div. Applied BioSci. Grad. Sch. Agric,, Kyoto Univ.3, Res. Cent. Glycobiotech., Ritsumeikan Univ.4) | |
| 1P048: | Hemimelic extra-toes (Hx) mutation gains a new cis-regulatory motif in limb-specific Shh enhancer ○Takanori Amano, Sagai Tomoko, Ayaka Okagaki, Toshihiko Shiroishi (NIG) | |
| 1P049: | Expression profile of hedgehog interacting protein suggests its involvement in the intestinal remodeling during Xenopus laevis metamorphosis ○Takashi Hasebe1, Mitsuko Kajita2, Atsuko ISHIZUYA-OKA1 (Dept. Biol., Nippon Med. Schl1, Dept. Mol. Biol., Inst. Gerontol., Nippon Med. Schl.2) | |
| 1P050: | Delta-like 3 (Dll3) does not substitute for Delta-like 1 (Dll1) in somitogenesis in vivo but modulates Dll1/Notch signaling in the posterior PSM ○Yu Takahashi1, Satoshi Kitajima1, Yukuto Yasuhiko1, Jun Kanno1, Yumiko Saga2 (NIHS1, NIG2) | |
| 1P051: | The malformation of mouse embryos cultivated with nicotine. ○Mikiko Miura, Junji Yodoi (IVR) | |
| 1P052: | DE-Cadherin- and MyosinID-dependent cell shape changes were involved in the laterality of the Drosophila embryonic gut ○Kiichiro Taniguchi, Tadashi Ando, Takashi Okumura, Reo Maeda, Naotaka Nakazawa, Shunya Hozumi, Kenji Matuno (Dept. Biol. Sci./Tec., Tokyo Univ. Sci.) | |
| 1P053: | Activation of Sox2 expression by enhancer N-1 at the posterior and of extending neural plate ○Megumi Yoshida, Tatsuya Takemoto, Masanori Uchikawa, Hisato Kondoh (Grad. Sch. of Frontier Biosci., Osaka Univ) | |
| 1P054: | The recovery of synchronous oscillation from randomness in the segmentation clock ○Yutaro Kii, Kana Ishimatsu, Daisuke Shirakawa, Hiroyuki Takeda (Dept. Biol. Sci, Univ. Tokyo) | |
| 1P055: | Two adjacent long-range enhancers regulate segmental Shh expression in epithelial linings of endoderm ○Tomoko Sagai1, Takanori Amano1, Masaru Tamura1, Yoichi Mizushina1, Hiromi Yamamoto1, Ayaka Okagaki1, Kenta Sumiyama2, Toshihiko Shiroishi1 (Mammal. Genet., Natl. Inst. Genet.1, Pop. Genet., Natl. Inst. Genet.2) | |
| 1P056: | Regulation of Sox3 in early neural development ○Naoko Nishimura, Yoshifumi Kamimura, Tatsuya Takemoto, Masanori Uchikawa, Hisato Kondoh (Grad. Sch. of Frontier Biosci., Osaka Univ.) | |
| 1P057: | Sox2 regulation at the divergence of neural and mesodermal lineages ○Tatsuya Takemoto, Megumi Yoshida, Masanori Uchikawa, Hisato Kondoh (Dev.Biol.Gr., Grad.Sch.of Frontier Bioscis., Osaka Univ.) | |
| 1P058: | in vitro vasculogenesis model revisited: measurement of VEGF diffusion process ○Takashi Miura1, Ryokichi Tanaka2, Kohei Shiota1 (Dept.of Anat.& Dev.Biol., Kyoto Univ.Grad.Sch.of Med.1, Department of Mathematics, Faculty of Science, Kyoto University2) | |
| 1P059: | Dynamic Modeling of Ureteric Tube Branching in Early Kidney Development ○Tsuyoshi Hirashima, Yoh Iwasa, Yoshihiro Morishita (Dept. of Biology, Kyushu Univ.) | |
| 1P060: | Doctor no and Ken and Barbie are involved in the left-right asymmetrical development of the Drosophila embryonic gut. ○Reo Maeda1, Shunya Hozumi1, Kiichiro Taniguchi1, Sasamura Takeshi1, Toshiro Aigaki2, Kenji Matsuno1 (Dept. of Biol. Sci./Tec., Tokyo Univ. of Sci.1, Dept. of Biol. Sci., Tokyo Metropolitan Univ.2) | |
| 1P061: | Formation of cerebellum in zebrafish and its genetic control ○Shuichi Kani1, YOUNG-KI Bae2, Takashi Shimizu1, Koji Tanabe1, Chie Satoh3, SHIN-ICHI Higashijima3, Masahiko Hibi1 (RIKEN CDB1, Cancer Experimental Branch, Division of Basic & Applied Sciences, Research Institute, National Cancer Center, Republic of Korea2, Ctr. for Integr. Biosci., Nat'l Inst. of Natural Scis3) | |
| 1P062: | Regulation of the Sox2 gene in early otic and nasal development ○Satoko Sugahara, Masanori Uchikawa, Hisato Kondoh (FBS) | |
| 1P064: | Protogenin (PRTG) regulates gastrulation cell movement mediated by cell adhesion. ○Kodai Ito1, Reiko Toyoda2, Harukazu Nakamura1, Yuji Watanabe1 (Tohoku Univ.1, Chicago University2) | |
| 1P065: | Functional analyses of Mab21l2 during heart development ○Yohei Saito1, Ryuichi Yamada2, Naoki Takahashi1,2 (Grad. Sch. Agr. LifeSci. Univ Tokyo1, Grad.Sch.Bio.Sci.,NAIST2) | |
| 1P066: | Pea3/Ets transcription factors for cerebellar differentiation ○Hidekiyo Harada1,2,3, Tatstuya Sato4, Harukazu Nakamura1,2 (IDAC, Tohoku Univ.1, Grad., Life Sic. Dict, Tohoku Unive2, JSPS3, Slon-kettering Institute4) | |
| 1P067: | Identification of planar cell polarity in the floor plate of the zebrafish neural tube ○Shusaku Kurisu1,3, Hironori Wada2, Satomi Nakayama1, Hitoshi Okamoto1 (RIKEN BSI1, Dept. of Env. Sci., Niigata Univ.2, JSPS Research Fellow3) | |
| 1P068: | Role of GDF11 during hindlimb field determination ○Ayumi Hattori, Takayuki Suzuki, Toshihiko Ogura (Tohoku Univ. IDAC) | |
| 1P069: | Analysis of Shh expression in the chick autopod ○Natsuka Wakamatsu, Takayuki Suzuki, Toshihiko Ogura (IDAC) | |
| 1P070: | Fgf8 for ephrinA2/A5 expression in the chick optic tectum ○Jun Tanaka1, Harada Hidekiyo1,2, Nakamura Harukazu1 (Tohoku univ.1, JSPS2) | |
| 1P071: | Roles of Nodal signaling in the embryo of the ascidian Ciona intestinalis ○Kaoru Mita1, Ryo Koyanagi2, Kaoru Azumi2, Shigeki Fujiwara1 (Fac. of Sci., Kochi Univ.1, Div. of Innovative Research, CRIS, Hokkaido Univ.2) | |
| 1P072: | Hypoxia-inducible abnormal spinal column development ○Kazuo Araki1,2, Hiroyuki Oksmoto2, Toshiyuki Yamada1,2 (NRIA. FRA,1, Fac. Biore. Mie Uni.2) | |
| 1P073: | Localization of left-sided pitx2 expression in flounder larval diencephalon and analysis of succeeding asymmetric development of brain and optic nerves ○Youhei Washio1, Masato Aritaki2, Yuichiro Fujinami2, Hisashi Hashimoto3, Tohru Suzuki1 (Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University1, Miyako Station, Fisheries Research Agency2, Bioscience and Biotechnology Center, Nagoya University3) | |
| 1P074: | The expression of Cdx2 changes according to the position of cells in mouse blastocyst formation ○Kouji Komatsu, Yo-ichi Nabeshima, Toshihiko Fujimori (Dept. Pathol. Tumor Biol., Grad. Sch. Med., Kyoto Univ.) | |
| 1P075: | A critical role of the somite for D-V patterning in the trunk region of medaka ○Toru Kawanishi, Atsuko Shimada, Hiroyuki Takeda (Dept. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., The Univ. of Tokyo) | |
| 1P076: | Drosophila respiratory tube connection requires an Arf-like GTPase for converting plasma membrane topology ○Ken Kakihara1,2, Shinmyozu Kaori1, Kato Kagayaki1, Wada Hosei1, Hayashi Shigeo1,2 (Riken CDB1, Graduate School of Science and Technology, Kobe University2) | |
| 1P077: | Siah-Interacting Protein SINUP Is Essential for Gastrulation Movements of Convergent Extension ○Kyeong-Won Yoo1, Hyunju Ro1, Chang-Joong Lee2, Myungchull Rhee1 (Chungnam Natl. Univ.1, Inha Univ.2) | |
| 1P078: | Hedgehog and Delta signaling differentially regulate expression of transcription factor genes that are required for anterior patterning in the spider Achaearanea embryo ○Masaki Kanayama1,2, Yasuko AKIYAMA-ODA2, Hiroki Oda2 (Osaka University1, BRH2) | |
| 1P079: | Golgi protein 181 participates in vesicular trafficking and regulates early Xenopus development ○Ayako Sedohara1, Shinji Komazaki3, Makoto Asashima1,2 (Dept.of Life Scis.(Biol.), Grad.Sch.of Art & Scis., Univ.of Tokyo1, ICORP project2, Dept. of Anatomy, Saitama Med. Sch.3) | |
| 1P080: | The Process of Flatfish Pigment Cell Development ○Toshiyuki Yamada, Masanori Okauchi, Kazuo Araki (NRIA) | |
| 1P081: | Morphogen receptor expression in the Drosophila wing patterning. ○Yuri Ogiso, Shoko Yoshida, Makoto Sato, Tetsuya Tabata (IMCB, Univ of Tokyo) | |
| 1P082: | Regulation mechanism of the Blimp-1 gene which plays an important role to determine pupation timing in Drosophila ○Kazutaka Akagi1, Moustafa Sarhan1, Hitoshi Ueda1,2 (Glad. Sch. of Nat. Sci. and Tech., Okayama Univ.1, Dept. of Biol, Fac. of Sci, Okayama Univ2) | |
| 1P083: | Synchronized oscillation and traveling wave in vertebrate segmentation ○Koichiro Uriu1, Yoshihiro Morishita2, Yoh Iwasa1 (Dept. Biology, Kyushu Univ.1, PRESTO Japan2) | |
| 1P084: | Left-right asymmetry for cardiac C-looping process in the chick embryo ○Hinako Kidokoro1, Masataka Okabe2, Koji Tamura3 (Graduate School of Life Sciences, Tohoku University1, The Jikei University School of Medicine2, Graduate School of Life Sciences, Tohoku University3) | |
| 1P085: | A dynamical model for Stylopod-Zeugopod boundary formation in vertebrate limb development ○Yoshihiro Morishita1, Yoh Iwasa2 (PRESTO, JST1, Kyushu Univ.2) | |
| 1P086: | hedgehog and patched control formation of two orthogonal axes in the early spider embryo ○Yasuko Akiyama-Oda, Hiroki Oda (JT Biohistory Res. Hall) | |
| 1P087: | Expression pattern of BMP signaling in the mouse embryonic gut and their roles in the smooth muscle differentiation ○Shigeko Torihashi1, Takako Hattori2, Hirotaka Hasegawa2, Takunori Ogaeri2, Masaaki Kurahashi2 (Dept.of Health Science, Nagoya Univ. Grad. Sch. of Med.1, Dept. of Anat. & Molec. Cell Biol. Nagoya Univ. Grad. Sch. of Med.2) | |
| 1P088: | Transcriptional regulation of the hox family genes with brpf1 is required for the establishment of pharyngeal segmental identity in medaka. ○Kenta Hibiya, Keiji Inohaya, Atsushi Kawakami, Akira Kudo (Dept.of Biol.Information, Tokyo Inst.of Technol.) | |
| 1P089: | InvE, a MAP kinase, regulates cell shape changes required for morphogenesis of the Volvox embryo ○Jun Kadota, Noriko Ueki, Ichiro Nishii (FRS, RIKEN) | |
| 1P090: | Differential expression and molecular interaction of regulatory genes in vertebrate myogenesis ○Rie Kusakabe1,2, Shigehiro Kuraku3, Kunio Inoue1, Shigeru Kuratani2 (Dept. Biol., Grad. Sch. Sci., Kobe Univ.1, RIKEN CDB2, Dept. Biol., Univ. Konstanz3) | |
| 1P091: | Network Evolution of Body Plans: Arthropod Segmentation ○Koichi Fujimoto1, Shuji Ishihara2, Kunihiko Kaneko1,2 (JST, ERATO Complex Systems Biology1, Dept. of Pure and Appl. Sci. Univ. of Tokyo.2) | |
| 1P092: | Positional adjustment of zebrafish primary motoneurons before axonogenesis ○Mika SATO-MAEDA, Masuo Obinata, Wataru Shoji (Dept. Cell Biol., IDAC, Tohoku Univ.) | |
| 1P093: | FGF signaling cascade in developing mammalian cerebral cortex ○Reiko Toyoda, Elizabeth Grove (Dept Neurobiology, Univ. of Chicago) | |
| 1P094: | The role of Semaphorin signaling in the projections of olfactory bulb axons ○Takahiko Kawasaki1,2, Tatsumi Hirata1,2 (NIG1, SOKENDAI2) | |
| 1P095: | Identification and characterization of a cis-regulatory module required for specific gene expression in a subset of GABA/glycinergic neurons of the Ciona intestinalis larva ○Koki Nishitsuji1, Takeo Horie1,2, Yuki Morimoto1, Yuki Miyamoto1, Yasunori Sasakura2, Takehiro G. Kusakabe1 (Grad. Sch. Life Sci., Univ. Hyogo1, Shimoda Mar. Res. Cent., Univ. Tsukuba2) | |
| 1P096: | Regenerating chemosensation in the planaria Dugesia japonica ○Clement Lamy, Kiyokazu Agata (Kyoto University - Biophysics) | |
| 1P097: | Identification of the downstream targets of single-minded underlying the development of Drosophila visual center ○Atsushi Sugie1, Daiki Umetsu2, Tetsuya Tabata1 (IMCB, Univ. of Tokyo1, MPI-CBG, Dresden, Germany2) | |
| 1P098: | Morphological diversity of dendrite is generated by class-specific transcription factors ○Yukako Hattori1, Kaoru Sugimura1,2, Daisuke Satoh3, Tadao Usui1, Tadashi Uemura1 (Grad. Sch. Biostudies, Kyoto Univ.1, Present address: BSI, RIKEN2, Grad. Sch. Science, Kyoto Univ.3) | |
| 1P099: | A Novel Repulsive Axon Guidance Protein, Draxin ○Yohei Shinmyo1, Shahidul Islam1, Tatsuya Okafuji1, Yuhong Su1,3, Iftekhar Bin Naser1,3, Giasudin Ahmed1,3, Sanbing Zhang1,3, Sandy Chen1, Hiroshi Kiyonari5, Takaya Abe5, Satomi Tanaka2, Ryuichi Nishinakamura2,3, Toshio Kitamura4, Hideaki Tanaka1,3 (Div. of Dev. Neurobiol., Kumamoto Univ.1, Division of Integrative Cell Biology, Institute of Molecular Embryology and Genetics, Kumamoto University2, Global COE "Cell Fate Regulation Research and Education Unit", Kumamoto University3, Division of Cellular Therapy, The Institute of Medical Science, The University of Tokyo4, Laboratory for Animal Resources and Genetic Engineering, Center for Developmental Biology, RIKEN Kobe5) | |
| 1P100: | Analysis of the role of mitochondrial fusion and fission in neuronal cell morphogenesis in Drosophila ○Taiichi Tsuyama, Asako Tsubouchi, Tadashi Uemura (Grad. Sch. Biostuides, Kyoto Univ.) | |
| 1P101: | Simultaneous knockdown of the group B1 sox genes in zebrafish embryos reveals their multifaceted roles from early embryonic patterning to neural development. ○Yuichi Okuda, Hisato Kondoh, Yusuke Kamachi (Grad.Sch.of Frontier Bioscis., Osaka Univ.) | |
| 1P102: | Characterization of the reeler brain by expression of molecular markers ○Hideyuki Dekimoto, Toshio Terashima, Yu Katsuyama (Kobe Univ., Grad. Sch. Med.) | |
| 1P103: | Fruitless and Longitudinal lacking coordinately specify the neurons required for courtship behavior of Drosophila ○Kosei Sato1, Seigo Shima2, Masayuki Koganezawa1, Gakuta Toba1, Daisuke Yamamoto1 (Graduate School of Life Sciences, Tohoku University.1, Advanced Institute for Science and Engineering, Waseda University2) | |
| 1P104: | Hidden developmental program of Rohon-Beard cells in mice ○Hiroshi Yajima, Keiko Ikeda, Shigeru Sato, Kiyoshi Kawakami (Biol. CMM Jichi) | |
| 1P105: | Role of Six1 and Six4 in cranial gangliogenesis ○Keiko Ikeda, Hiroshi Yajima, Makoto Yamakado, Kiyoshi Kawakami (Biol. Jichi) | |
| 1P106: | Contribution of Lim-homeobox gene to organization of planarian CNS Tetsutaro Hayashi1, Osamu Nishimura1, Jeremy Pulvers2, Kiyokazu Agata3, ○Hiroshi Tarui1 (RIKEN, CDB1, Max-Planck-Institute2, Kyoto University3) | |
| 1P107: | A Runt family transcription factor is differentially required for distinct classes of the olfactory sensory neurons in Drosophila ○Keita Endo, Kei Ito (IMCB, Univ. of Tokyo) | |
| 1P108: | Ontogeny of glutamatergic, GABA/glycinergic, and cholinergic neurons in the Ciona intestinalis larva ○Yuki Morimoto1, Takeo Horie1,2, Yasunori Sasakura2, Takehiro G. Kusakabe1 (Grad Sch Life Sci, Univ. Hyogo1, Shimoda Mar. Res. Cent., Univ. Tsukuba2) | |
| 1P109: | Gamma tubulin and microtubule-anchor protein in the dendrite development Yusaku Ohama1, Kazuto Hirata2, ○Kensuke Hayashi1 (Life Sci. Inst., Sophia Univ.1, Chiba Univ.2) | |
| 1P110: | Roles of Wnt signal in development of Drosophila mushroom body ○Kazumichi Shimizu, Makoto Sato, Tetsuya Tabata (IMCB) | |
| 1P111: | Remodeling of neuronal dendritic arbors in the Drosophila peripheral nervous system Azusa Fujimoto1, ○Kohei Shimono1, Taiichi Tsuyama1, Yukako Hattori1, Misato Yamamoto-Kochi1, Ken-ichi Kimura2, Tadashi Uemura1 (Graduate School of Biostudies, Kyoto University1, Hokkaido University of Education2) | |
| 1P112: | Study of Drosophila bristle pattern formation: Appearance and elimination of the ectopic sensory organ precursor cells ○Akiko Koto1, Erina Kuranaga1,2, Masayuki Miura1,2 (Dept. Genetics, Grad. Sch. Pharmaceutical Sci. , Univ. Tokyo1, CREST, JST2) | |
| 1P113: | Ci-POU-IV, a POU domain transcription factor, is required for development of epidermal glutamatergic neurons in the Ciona intestinalis larva ○Takako Suzuki1, Takeo Horie1,2, Koki Nishitsuji1, Yasunori Sasakura2, Takehiro G. Kusakabe1 (Grad. Sch. Life Sci., Univ. Hyogo1, Shimoda Mar. Res. Cent., Univ. Tsukuba2) | |
| 1P115: | Establishment of the topographic relationship between neurons and neuromasts in the zebrafish lateral line system ○Akira Sato, Sumito Koshida, Hiroyuki Takeda (Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, University of Tokyo) | |
| 1P117: | Autotaxin, a phospholipids-generating enzyme, is regulated by Pax6 in the chicken brain development ○Hitomi Fukui, Mayumi Okamoto, Yoshifumi Yutoh, Shuang Song, Sumihare Noji, Hideyo Ohuchi (Department of Biological Science and Technology, University of Tokushima) | |
| 1P118: | Functional analysis of Fgf19 in the chicken embryonic retina ○Mayumi Okamoto, Yuki Yamahoshi, Shuang Song, Sumihare Noji, Hideyo Ohuchi (Department of life system, University of Tokushima) | |
| 1P119: | Enhancer trap screening for factors controlling the morphogenesis and functional differentiation of the Drosophila mushroom body ○Takashi Abe, Yuko Maeyama, Haruhiko Kawamori, Makoto Sato, Satoshi Murakami, Tetsuya Tabata (IMCB, Univ. of Tokyo) | |
| 1P120: | Analysis of glial cell sub-lineages in the developing mouse central nervous ystem ○Tetsushi Kagawa1, Kimi Araki2, Naoki Takeda3, Takeshi Shimizu1, Tetsuya Taga1 (IMEG, Kumamoto Univ.1, IMEG, Kumamoto Univ.2, CARD, Kumamoto Univ.3) | |
| 1P121: | Fruitless-Bonus complex recruits chromatin regulators, HP1 and Rpd3, each with opposing effects on neural masculinization in Drosophila. ○Hiroki Ito1,2,3, Masayuki Koganezawa1, Manabu Ote1,2, Ken Matsumoto2, Minoru Tateno2, Chihiro Hama3, Daisuke Yamamoto1,2 (Tohoku University Graduate School of Life Sciences1, Waseda University Advanced Institute for Science and Engineering2, RIKEN Center for Developmental Biology3) | |
| 1P122: | The promoter analysis of the ascidian neural tube specific gene II ○Yoshihiro Tamari1, Yuki Kitaura1, Takahito Nishikata1,2 (Fac.Sci.Eng., Konan Univ.1, FIBER., Konan Univ.2) | |
| 1P123: | Premature neurogenesis in the Pax6 heterozygous mutant cerebral cortex ○Toshiko Umeda1, Tadashi Nomura1, Fumikazu Suto1, Noriko Osumi1,2 (Div. Dev. Neurosci, Tohoku Univ. Sch. of Med.1, CREST/JST2) | |
| 1P124: | Roles of mitotic spindle orientation in neuroepithelial progenitors during mammalian brain development ○Daijiro Konno1,2, Go Shioi1,2, Atsunori Shitamukai1,2, Fumio Matsuzaki1,2 (RIKEN CDB1, CREST JST2) | |
| 1P125: | atg8a and thread (DIAP-1) are candidates of modifiers of spinster, a mutation that causes enhanced mate refusal in female Drosophila ○Akira Sakurai1, Yoshiro Nakano2, Masayuki Koganezawa1, Daisuke Yamamoto1 (Graduate School of Life Sciences, Tohoku University1, Department of Genetics, Hyogo College of Medicine2) | |
| 1P126: | Mating acceptance of medaka depending on visual information and analysis of the neural basis ○Teruhiro Okuyama1, Yuji Suehiro1, Haruka Imada1, Atsuko Shimada1, Kiyoshi Naruse2, Hiroyuki Takeda1, Takeo Kubo1, Hideaki Takeuchi1 (Dept.of Biol.Scis., Grad.Sch.of Sci., Univ.of Tokyo1, Natl. Inst. Basic Biol.2) | |
| 1P127: | Contactin 1 knockdown induces abnormal development of the trigeminal nerve in Xenopus embryos ○Naoko Fujita, Saburo Nagata (JWU) | |
| 1P128: | Expression analysis of the non-canonical opsin genes during chicken retinal development ○Akira Takagi, Sayuri Tomonari, Kyoichi Migita, Sumihare Noji, Hideyo Ohuchi (Dept. of Life Systems, Inst. of Tech. and Sci., Univ. of Tokushima) | |
| 1P129: | A Role of the Mitochondria-Dependent Activation of Caspases in the development of Olfactory Sensory Neurons ○Shizue Ohsawa1, Keisuke Kuida2, Hiroki Yoshida3, Masayuki Miura1 (Dept. Genetics, Sch. Pharma. Sci., Univ. Tokyo1, Dept. Biol., Vertex Pharmaceuticals, Cambridge, MA2, Dept. Biomol. Sci., Fac. Medicine, Saga Univ. Saga3) | |
| 1P130: | Photostimulation-dependent upregulation of 1020HH gene expression during planarian brain regeneration ○Tomomi Takano1,4, Umesono Yoshihiko2, Hayashi Tetsutaro3, Tarui Hiroshi3, Kuratani Shigeru4, Agata Kiyokazu2 (Kobe University1, Kyoto University2, GRAS, CDB, RIKEN3, Lab. Evol.Morph, CDB, RIKEN4) | |
| 1P131: | Concentric zones, cell migrations and neuronal circuits in the Drosophila brain ○Makoto Sato1, Yusuke Kitada2, Miyako Tai2, Daiki Umetsu2, Tetsuya Tabata2 (FSO, Kanazawa Univ1, IMCB, Univ. of Tokyo2) | |
| 1P132: | Transcriptional regulation of the zebrafish class V POU gene, pou2, in the midbrain-hindbrain region during early development. Mst. Parvin1, Noriko Okuyama1, Fumitaka Inoue1, Md. Islam1, Atsushi Kawakami2, Hiroyuki Takeda3, ○Kyo Yamasu1 (Div. Life Sci., Grad. Sch. Sci. Eng., Saitama Univ.1, Dept. Biol. Information, Tokyo Inst. Tech.2, Dept. Biol. Sci., Grad. Sch. Sci., Univ. Tokyo3) | |
| 1P133: | Differential expression of class I OR genes during frog metamorphosis ○Tosikazu Amano, Jean Gascuel (CESG/CNRS) | |
| 1P134: | Sequence analysis of small non-coding RNAs present in preimplantation mouse embryos ○Yusuke Ohnishi1,2, Atsushi Toyoda3, Yasushi Totoki3, Katsushi Tokunaga1, Yoshiyuki Sakaki3, Hirohiko Hohjoh2 (Hum. Genet., Graduate School of Medicine, Univ. Tokyo1, NCNP2, RIKEN Yokohama Institute3) | |
| 1P135: | Chromosomal mapping of regulatory genes for construction of a chordate embryo ○Eiichi Shoguchi1,2, Makoto Hamaguchi1, Satoh Nori1,2 (Kyoto Univ.1, OIST2) | |
| 1P136: | Ars insulator enhances I-SceI meganuclease-mediated transgenic efficiency in sea urchin, Hemicentrotus pulcherrimus ○Hiroshi Ochiai1, Naoaki Sakamoto1, Kenichi Suzuki2, Koji Akasaka3, Takashi Yamamoto1 (Dept. of Math. and Life Sci., Grad. School of Sci., Hiroshima Univ.1, Dept. of Biol. Sci., Grad. School of Sci., Hiroshima Univ.2, Misaki Marine Biol. Stat., Grad. School of Sci., Univ. of Tokyo3) | |
| 1P137: | Molecular signature of the physical interaction with the GCN5 in the mouse MII oocytes: Implication for the roles of nuclear reprogramming in mouse oocytes. ○Rieko Umeda, Toshiaki Noce, Tomoharu Osada (MITILS) | |
| 1P138: | Development of photochemical DNA/RNA manipulation toward its application for developmental biology ○Yoshinaga Yoshimura1, Yuta Taya2, Kenzo Fujimoto1,2 (JST1, JAIST2) | |
| 1P139: | Mass spectrometry-based proteomic analysis for ascidian early embryogenesis ○Lixy Yamada1, Hisaaki Taniguchi1,2 (Inst. for Enzyme Res. the Univ. of Tokushima1, BIRD, JST2) | |
| 29 May, 12:10 - 18:30 & 30 may, 09:00 - 13:00, Exhibition Room |
| Poster 2 : | Discussion time: 29 May | 16:30 - 17:30 for even No. posters. 17:30 - 18:30 for odd No. posters. |
| 2P001: | Immunohistochemical study of muscle development in the Japanese flounder, Paralichthys olivaceus ○Susumu Uji1, Tohru Suzuki2, Tadahide Kurokawa1 (NRIA1, Laboratory of Bioindustrial Informatics, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University2) | |
| 2P002: | Neural induction of Nematostella vectensis: an essential role of β-Catenin pathway ○Hiroshi Watanabe, Bianca Bertulat, Toshitaka Fujisawa, Thomas W Holstein (Heidelberg Institute of Zoology) | |
| 2P003: | Non-neuronal cholinergic system involved in regulation of the developmental processes in Hydra ○Toshio Takahashi1, Mamiko Hirose2, Chiemi NISHIMIYA-FUJISAWA3, Toshitaka Fujisawa3 (Suntory Inst. for Bioorg. Res.1, Fac. of Sci. Ryukyus Unv.2, Dept. of Mol. Evo. and Genomics, Heidelberg Univ.3) | |
| 2P004: | Comparative and experimental analysis of jaw muscle morphogenesis in quail and duck: a basis for understanding developmental mechanisms underlying evolutionary change ○Masayoshi Tokita1,2, Richard Schneider1 (UCSF1, Kyoto Univ.2) | |
| 2P005: | Developmental inhibitor secreted by Acytostelium subglobosum, a primitive social amoeba without cell differentiation ○Kyoko Uchi, Hidekazu Kuwayama, Ryuji Yoshino, Hideko Urushihara (Graduate School of Life and Environmental Sciences, Univ. of Tsukuba) | |
| 2P006: | Characterization and transgenic rescue of the medaka spontaneous mutant Double anal fin. ○Yuuta Moriyama1, Atsuko Shimada1, Xueyan Shen2, Kiyoshi Naruse2, Hiroyuki Takeda1 (Dept. Biol. Sci., Univ. Tokyo1, Natl. Inst Basic Biol. Lab. of Biores.2) | |
| 2P007: | Reevaluation of the tracheal gill - stylus theory for the insect wing origin by comparing the expression of wing-related genes in basal insects ○Nao Niwa, Ai Akimoto-Kato, Shigeo Hayashi (Morphogenetic Signaling, RIKEN CDB) | |
| 2P008: | Analysis of the expression pattern and cluster structure of Hox genes in feather star Oxycomanthus japonicus ○Toko Tsurugaya1, Daisuke Kurokawa1, Tomoko Shibata1, Tatsuya Ota2, Kazuho Ikeo3, Akasaka Koji1 (MMBS1, Sokendai2, NIG3) | |
| 2P009: | Isolation of noggin-like gene from Pelmatohydra oligactis: Possible implications in the study of evolutionary origin of neural induction ○Kalpana Chandramore1, Saroj Ghaskadbi2, Surendra Ghaskadbi1 (ARI1, UoP2) | |
| 2P010: | Heterotypy in the N-terminal region of Growth/Differentiation Factor 5 (GDF5) mature protein during teleost evolution ○Koji Fujimura1, Yohey Terai1, Naoya Ishiguro2,3, Masaki Miya4, Mutsumi Nishida2, Norihiro Okada1 (Grad. Sch. Biosci. Biotechnol., Tokyo Inst. Technol.1, Ocean Res. Inst., Univ. Tokyo2, Dep. Env. Biotechnol. Front. Eng., Fukui Univ. Technol.3, Dep. Zool., Nat. Hist. Mus. Inst., Chiba4) | |
| 2P011: | Relationship between the duplication and the temporal expression pattern of Hox cluster ○Jun Nakabayashi (Sokendai) | |
| 2P012: | Elav expression and the nervous system development of crinoids ○Akihito Omori, Daisuke Kurokawa, TOMOKO F. Shibata, Shonan Amemiya, Koji Akasaka (MMBS, Univ. Tokyo) | |
| 2P013: | Analysis of conservrd function of mab21 gene in eye development ○Ayumi Nakazaki1, Takuya Kojima1, Hidetoshi Saiga2, Takeo Horie3, Yasunori Sasakura3, Naoki Takahashi1 (Grad.Sch.Agr.LifeSci.,Univ Tokyo1, Grad. Sch. Sci.,Univ Tokyo Metropolitan2, Shimoda Marine Research Center, Univ Tsukuba3) | |
| 2P014: | Evolutionary conservation of the developmental mechanism for the most-anterior digit formation in amniote limbs ○Asaka Uejima, Miyuki Noro, Taiji Yasue, Takanori Amano, Koji Tamura (Grad. Sch. Life Sci., Tohoku Univ.) | |
| 2P015: | Evolution of Six1 enhancers in vertebrates ○Shigeru Sato1, Keiko Ikeda1, Rika Nakayama2, Tomoe Bunno2, Yasunori Hayashibara2, Shin-ichi Aizawa2, Kiyoshi Kawakami1 (Div. of Biol., Jichi Med. Univ.1, CDB, RIKEN2) | |
| 2P016: | Cloning and characterization of microRNAs in the cricket, Gryllus bimaculatus ○Takahito Watanabe, Taro Nakamura, Taro Mito, Hideyo Ohuchi, Sumihare Noji (Dept. of Life Systems, Inst. of Tec. and Sci., Univ. of Tokushima) | |
| 2P017: | Novel Peripheral Neuronal Structure Revealed by Confocal and Transmission Electron Microscopies in Ascidian Larvae ○Hiroshi Terakubo, Nakajima Yoko, Hotta Kohji, Oka Kotaro (KEIO UNIV.) | |
| 2P018: | Evolutionary conservation for the concordant regulation of Engrailed2 and Canopy1 in the Midbrain-Hindbrain Boundary ○Hisaya Kakinuma1, Sara Trowbridge2, Motoko Aoki1, Hitoshi Okamoto1 (RIEKN BSI Lab. for DGR1, Harvard college2) | |
| 2P019: | Searches for a genomic sequence that governs species differences in the neural induction of a male-specific muscle in Drosophila. ○Sakino Takayanagi1, Lukacsovich Tamas2, Manabu Ote1, Gakuta Toba1, Daisuke Yamamoto1 (Graduate School of Life Sciences, Tohoku University1, Depertment of Developmental and Cell Biology University of California, Irvine, USA2) | |
| 2P020: | Acquisition of a novel organ involved in regulation of calcium concentration in the blood during vertebrate evolution ○Takanori Shono1, Akiko OGURA NODA2,3, Masataka Okabe1 (Jikei University1, AIST2, JBIC3) | |
| 2P021: | Heart development and chamber evolution in reptiles ○Kazuko KOSHIBA-TAKEUCHI1, JUN K Takeuchi1, BENOIT G Bruneau2 (GEI, Tokyo Tech1, GICD, UCSF2) | |
| 2P022: | Comparative analysis of Zic expression profiles in protostome worms ○Jun Aruga1, Hirokazu Takahashi1, Yuri S Odaka1, Hidetaka Furuya2, Takashi Shimizu3 (Lab. Comparat. Neurog., RIKEN BSI1, Dept. Biol., Grad. Sch.Sci., Osaka Univ.2, Div. Biol. Sci., Grad. Sch. Sci., Hokkaido Univ.3) | |
| 2P023: | Roles of the orthodenticle gene in the anterior patterning during early embryogenesis of the cricket Gryllus bimaculatus ○Shotaro Ogawa1, Taro Mito1, Takuya Matsuki1, Taro Nakamura1, Tetsuya Bando1, Hideyo Ohuchi1,2, Sumihare Noji1,2 (Development of Biological Science and Technology, University of Tokushima1, Tokushima Intellectual Cluster2) | |
| 2P024: | In silico analyses of gene structures and cis-regulatory regions of developmental regulatory genes of the cricket Gryllus bimaculatus ○Takuya Matsuki1, Taro Mito1, Shotaro Ogawa1, Taro Nakamura1, Tetsuya Bando2, Hideyo Ohuchi1,2, Sumihare Noji1,2 (Department of life system, The Univ. of Tokushima1, Tokushima Intellectual Cluster2) | |
| 2P025: | Developmental mechanisms regulating species-specific lateral line patterns of the teleost caudal fin ○Hironori Wada1, Satoshi Hamaguchi2, Mitsuru Sakaizumi1,2 (Center for Transdisciplinary Research, Niigata University1, Faculty of Science, Niigata University2) | |
| 2P026: | Activin A induces differentiation of the medaka embryonic cells into cardiomyocytes in vitro ○Masao Hyodo1, Shinji Makino2, Yasunori Awaji1, Yohei Sakurada1, Tomoichi Ohkubo3, Mitsusige Murata2, Keiichi Fukuda2, Michio Tsuda4 (Dept. Biol. Sci. Technol., Tokai Univ.1, Dept. Regen. Med. Adv. Card. Therap., Keio Univ. Sch. Med.2, Teach. Res. Supp. Ctr., Tokai Uni . Sch. Med.3, Dept. Mol. Life Sci., Tokai Univ. Sch. Med.4) | |
| 2P027: | Expression patterns of Eya1 and Eya2 in chick early development Tadashi Ishihara, Keiko Ikeda, Shigeru Sato, Hiroshi Yajima, ○Kiyoshi Kawakami (Div. Biol., CMM, Jichi Med. Univ.) | |
| 2P028: | Functional analysis of Lgr4/Gpr48 in the epithelial tissue ○Yasuaki Mohri1, Shigeki Kato1,4, Tsuyoshi Matsuo1, Eisaku Ogawa2, Akihiro Umezawa3, Ryuhei Okuyama2, Katsuhiko Nishimori1 (Lab. of Mol. Biol., Grad. Sch. of Agr. Sci., Tohoku Univ.1, Dept. of Dermatol., Grad. Sch. of Med., Tohoku Univ.2, Natl. Res. Inst. for Child Health and Dev.3, Dept. of Mol. Genet., Inst. of Biomed. Sci., Fukushima Med. Univ.4) | |
| 2P029: | Dre-miR-143 regulates the formation of ventricle and outflow tract. ○Kota Miyasaka, Yasuyuki Kida, Toshihiko Ogura (IDAC, Tohoku Univ.) | |
| 2P030: | The Roles of Hedgehog signaling in development of the mouse neocortex Munekazu Komada, Hirotomo Saitsu, Masato Kinboshi, Takashi Miura, Kohei Shiota, ○Makoto Ishibashi (Dept.of Anat.& Dev.Biol., Grad.Sch.of Med., Kyoto Univ.) | |
| 2P031: | The role of Dlgh1 (Discs Large Homolog-1) in organogenesis. ○Akiko Kogo1, Tetsu Akiyama2, Takao Senda1 (Dept. of Anatomy I, Fujita Health Univ. Sch. of Med.1, Lab. of Molecular and Genetic Information, IMCB, Univ. of Tokyo2) | |
| 2P032: | Mechanisms of Sox2 regulation underlying sensory placodal development Yuka Saigou, ○Masanori Uchikawa, Hisato Kondoh (Grad.Sch.of Frontier Bioscis., Osaka Univ.) | |
| 2P033: | Morphogenesis and origin of the cartilaginous elements of the anterior neurocranium during chick development. ○Naoyuki Wada1, Shigeru Kuratani2, Tsutomu Nohno1 (Dept Mol Dev Biol, Kawasaki Med Sch1, RIKEN, CDB2) | |
| 2P034: | Analysis of the Dharma-medaka mutant, which shows a defect in formation and/or maintenance of intervertebral region ○Keiji Inohaya1, Yoshiro Takano2, Akira Kudo1 (Dept.of Biological Inforamtion, Tokyo Inst.of Technol.1, Dept. of Hard Tissue Engineering, Tokyo Medical and Dental University2) | |
| 2P035: | Expression of myogenin, but not of MyoD, is temperature-sensitive in mouse skeletal muscles ○Ai Shima, Ryoichi Matsuda (Department of Life Sciences, Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo) | |
| 2P036: | Functional analysis of Angptl3 in the chick liver development ○Daisuke Niki, Ken Matsumoto, Kenjiro Katsu, Yuji Yokouchi (Pattern Formation, IMEG) | |
| 2P037: | Identification and expression of a novel nuclear factor, val, in Xenopus embryo Yuhta Takahashi2, Yumi Izutsu1, ○Mitsugu Maeno1 (Dept.of Biol., Fac.of Sci., Niigata Univ.1, Gra. Sch. Sci. Tech., Niigata Univ.2) | |
| 2P038: | Xenopus tadpole-derived XL-B4 myoblast cells transplanted into tadpole tails and limbs ○Takako Ishii1, Shutaro Takayama1, Kei Tamura1, Makoto Mochii2, Tadayoshi Shiba1, Nobuhiko Takamatsu1, Michihiko Ito1 (Sch. Sci., Dept. Biosci., Kitasato Univ.1, Dept. Life Sci., Gradu. Sch. Life Sci., Univ. of Hyogo2) | |
| 2P039: | Development Of Epibranchial Placode Derived Sense Organs In The Chick ○Paul ONeill1, Clare Baker2, Raj Ladher1 (CDB1, University of Cambridge2) | |
| 2P040: | Ripply3 plays essential roles in pharyngeal development ○Tadashi Okubo, Akinori Kawamura, Jun Takahashi, Akiko Ohbayashi, Shinji Takada (Okazaki Institute for Integrative Bioscience, National Institutes of Natural Sciences) | |
| 2P041: | Analysis of zebrafish mutant morendo showing defects of the digestive organ formation ○Shunya Hozumi1, Mitsuko Ogata2, Akio Yoshizawa2, Tohru Ishitani2, Makiko Tsutsumi2, Atsushi Kuroiwa2, Motoyuki Itoh2, Yutaka Kikuchi1 (Dep. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Hroshima Univ.1, Div. of Biol. Sci., Grad. Sch, of Sci., Nagoya Univ.2) | |
| 2P042: | Analyses of the mechanism of dorsal pancreas specification in the early chick endoderm ○Keiichi Katsumoto1,5, Kimiko Fukuda2, Wataru Kimura2,6, Kenji Shimamura3, Sadao Yasugi2,4, Shoen Kume1,5 (Division of Stem Cell Biology, Department of Regeneration of Medicine, Institute of Molecular and Embryology and Genetics, Kumamoto University.1, Faculty of Urban Liberal Arts, Tokyo Metropolitan University.2, Division of Morphogenesis, Department of Embryogenesis, Institute of Molecular and Embryology and Genetics, Kumamoto University.3, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Teikyo Heisei University.4, Global COE, Institute of Molecular and Embryology and Genetics, Kumamoto University.5, School of Medicine, Hamamatsu University.6) | |
| 2P043: | Phenotypic analysis of zebrafish mutant legato that shows defects of the digestive organ formation ○Rie Asada1, Mitsuko Ogata2, Shunya Hozumi1, Akio Yoshizawa2, Tohru Ishitani2, Makiko Tsutsumi2, Atsushi Kuroiwa2, Motoyuki Itoh2, Yutaka Kikuchi1 (Dep. of Biol. Sci., Grad. Sch. of Sci., Hiroshima Univ.1, Div. of Bio. Sci., Grad. Sch. of Sci., Nagoya Univ.2) | |
| 2P044: | A wave of EGFR signaling determines cell alignment and intercalation in the Drosophila tracheal placode ○Mayuko Nishimura1, Yoshiko Inoue2, Shigeo Hayashi1 (RIKEN CDB1, Gurdon Institute, University of Cambridge2) | |
| 2P045: | A short peptide gene, polished rice, controls Drosophila metamorphosis through intercellular communication. ○Yoshiko Hashimoto1, Takefumi Kondo1,2, Yuji Kageyama1,3 (NINS NIBB OIIB1, JSPS2, PRESTO, JST3) | |
| 2P046: | Characterization of the medaka mutant which displays abnormalities in hematopoiesis ○Akemi Moriyama, Satoshi Ohisa, Akira Kudo (Department of Biological Information, Tokyo Institute of Technology) | |
| 2P047: | Kif-k, a kinesin family gene, regulates Gdnf maintenance and controls ureteric bud attraction in kidney development ○Yukako Uchiyama1,2, Toshiaki Inenaga1, Shuji Inoue1,2, Chiyoko Kobayashi1, Ryuichi Nishinakamura1,2 (IMEG1, GCOE Kumamoto2) | |
| 2P048: | Analysis of the origin of the ventral pancreas ○Kumi Matsuura, Keiichi Katsumoto, Shoen Kume (Division of Stem Cell Biology, Department of Regeneration Medicine, IMEG, Kumam) | |
| 2P049: | A functional screen for genes involved in Xenopus pronephros development ○Junichi Kyuno, Karine Massé, Elizabeth Jones (Warwick University) | |
| 2P050: | Analysis of the cis-regulatory element of Fgf10 gene responsible for the limb specific expression ○Atsushi Kuroiwa, Ayumi Tanaka, Ikuhisa Nakanishi, Mie Hirano, Shigeki Yamamoto, Yo-ichi Shiraishi (Div.of Biol.Sci., Grad.Sch.of Sci., Nagoya Univ.) | |
| 2P051: | Analysis of multiple function of Mitf in chick RPE development ○Nagaharu Tsukiji1, Kazuhisa Takeda2, Shigeki Shibahara2, Hiroaki Yamamoto1 (Grad. Sch. of Life Scis., Tohoku Univ.1, Department of Molecular Biology and applied Phisiology, Graduate School of Medicine, Tohoku University2) | |
| 2P052: | In vivo imaging for osteoclasts in medaka, showing the evidence of bone modeling ○Masahiro Chatani, Keiji Inohaya, Akira Kudo (Tokyo Institute of Technology) | |
| 2P053: | Identification of a novel stromal diffusible factor determining epithelial cell fate decision ○Tomohiro Umezu, Yasuhiro Tomooka (Dept. of Biol. Sci. and Tech., Tokyo Univ. of Science) | |
| 2P054: | Pro-BMP roles of crossveinless 2 are required for metanephric mesenchyme condensation in a Bmp7-dependent manner ○Makoto Ikeya, Kumi Fukushima, Masako Kawada, Yoshiki Sasai (RIKEN CDB) | |
| 2P055: | Endothelin receptor type A-lacZ-knock-in mice may reveal a distinct cell lineage in heart development ○Rieko Asai1, Takahiro Sato1, Tomokazu Amano2, Yumiko Kawamura1, Yukiko Kurihara1, Hiroki Kurihara1 (Dept. of Phys. Chem. and Meta., Grad. Sch. of Med., the Univ of Tokyo1, Dept. of Dev. and Med. Tech. (Sankyo), Grad. Sch. of Med., the Univ of Tokyo2) | |
| 2P056: | Zac1 is an essential cardiac transcription factor ○Shinsuke Yuasa1,2, Takeshi Onizuka1,2, Kenichiro Shimoji1,2, Yohei Ohno1,2, Mie Hara2, Satoshi Ogawa1, Keiichi Fukuda2 (Cardiology Division, Department of Internal Medicine, Keio University School of Medicine1, Department of Regenerative Medicine and Advanced Cardiac Therapeutics, Keio University School of Medicine2) | |
| 2P057: | ENU-based Gene-Driven Mouse Mutagenesis, yet another reverse genetics infrastructure for coding as well as non-coding regions ○Takuya Murata1,2, Yoshiyuki Sakuraba2, Ryutaro Fukumura1,2, Shigeru Makino1,2, Ryo Takahashi2, Yuji Nakai1,2, Hideki Kaneda1,2, Naomi Fujimoto2, Keiko Tsuchihashi2, Kumiko Karouji2, Ai Nakahara2, Taichi Yamaguchi2, Emi Nakayama2, Norie Uemura2, Hayato Kotaki1,2, Kana Nakamura2, Tetsuo Noda1,2, Shigeharu Wakana1,2, Toshihiko Shiroishi2, Yoichi Gondo1,2 (RIKEN BRC1, RIKEN GSC2) | |
| 2P058: | Tead4 is required for specification of trophectoderm in pre-implantation mouse embryos ○Noriyuki Nishioka1, Shinji Yamamoto1, Kazuki Nakao2, Kenjiro Adachi3, Hiroshi Kiyonari2, Hiroko Sato1, Atsushi Sawada1,4, Hitoshi Niwa3, Hiroshi Sasaki1 (Lab.for Embryonic Induction, Ctr.for Dev.Biol., RIKEN Kobe1, Laboratory for Animal Resources and Genetic Engineering, Center for Developmental Biology, RIKEN Kobe2, Laboratory for Pluripotent Cell Studies, Center for Developmental Biology, RIKEN Kobe3, Department of Biological Sciences, Vanderbilt University4) | |
| 2P059: | Nanos2 plays an essential role in the maintenance of spermatogonial stem cells ○Aiko Sada1, Atsushi Suzuki3, Yumiko Saga1,2 (Sokendai, Genetics1, NIG, Mam. Dev2, IRC3) | |
| 2P060: | Characterization of sperm matrix metalloproteinase (MMP) indispensable for Xenopus fertilization ○Tomoyasu Yoshikawa, Shuichi Ueno, Yasuhiro Iwao (Mol. Dev. Biol.,Applied Mol. BioSci.,Yamaguchi Univ.) | |
| 2P061: | Functional analysis of Samuel in somatic cells during spermatogenesis ○Hiroyuki Kose1,2, Masataka Okabe2,3, Kozo Matsumoto1, Yasushi Hiromi2 (University of Tokushima1, National Institute of Genetics2, The Jikei University3) | |
| 2P062: | Fertilization and germ plasm in the lancelet from the Ariake Sea, Japan ○Makoto Urata, Kunifumi Tagawa, Kinya Yasui (Marine Biological Laboratory, Grad. Sch. of Sci., Hiroshima Univ.) | |
| 2P063: | Cell-free system to measure cytoplasmic Ca2+ increase necessary for egg activation in amphibian fertilization ○Mari Kawazoe, Tuichirou Harada, Shuichi Ueno, Yasuhiro Iwao (Mol. Dev. Biol.,Applied Mol. BioSci.,Yamaguchi Univ.) | |
| 2P064: | Epidermal growth factor mediates spermatogonial proliferation in newt testis ○Keisuke Abe, Yuki Nakayama, Ko Eto, Shin-ichi Abe (Kumamoto Uni sci and Tech) | |
| 2P065: | Nanos3-3'UTR is required for translational suppression of Nanos3 in mouse embryonic somatic cells ○Hitomi Suzuki1, Saga Yumiko1,2 (SUT1, NIG2) | |
| 2P066: | DNA demethylation regulates primordial germ cells-specific expression of mil-1 gene in mouse ○Kentaro Mochizuki, Yasuhisa Matsui (CRCBR, IDAC, Tohoku Univ.) | |
| 2P067: | In vitro development and analysis of embryos reconstructed with monkey (Macaca Fascicularis) cell nucleus and rabbit enucleated oocyte. ○Madoka Ozawa1, Toshiyuki Takehara1, Takayuki Yamochi2, Yuki Miyamoto3, Syunsuke Ito3, Naoto Fukunaga3, Yoshiko Tsuzimoto3, Makoto Takenoshita2, Satoshi Kisigami3, Kazuya Matsumoto3, Kazuhiro Saeki3, Akira Iritan3, Yoshihiko Hosoi3 (Grad sch of B.O.S.T,Kinki Univ1, Wakayama Research Institute, Keari Co., Ltd.2, Dep of B.O.S.T, Kinki Univ3) | |
| 2P068: | A family of CCCH-type zinc-finger proteins is essential for oocyte maturation and embryonic development in Caenorhabditis elegans ○Masumi Shimada, Hiroyuki Kawahara (TMU) | |
| 2P069: | Gene expression profiling and function of Nanos2 in mouse germ cells ○Rie Saba1, Atsushi Suzuki1,2, Hitomi Suzuki3, Aiko Sada4, Yumiko Saga1,3,4 (NIG1, IRS, Yokohama National Univ.2, Dept. Biol. Sci., Grad. Sch. Sci., Univ. Tokyo3, Dept. Genetics, SOKENDAI4) | |
| 2P070: | Nanos stabilization requires pgc-mediated transcriptional repression in Drosophila primordial germ cells ○Kazuko Hanyu-Nakamura, Hiroko Sonobe-Nojima, Akira Nakamura (Lab. for Germline Development, RIKEN CDB) | |
| 2P071: | Genome-wide search for cell-fusion related genes based on DNA microarray analysis in Dictyostelium Tomoe Satoh1, ○Kentaro Saeki1, Tetsuya Muramoto1, Jason Skeleton2, Rob Kay2, Hidekazu Kuwayama1, Hideko Urushihara1 (University of Tsukuba1, Sanger Center, UK2) | |
| 2P072: | Expression of stem and germ cell marker in juvenile bovine testis and its primary culture ○Koushirou Moriki1, Youhei Tazuhara1, Shunji Taniguchi1,2, Hiroko Kawamura1, Masayuki Anzai3, Hiromi Kato3, Kazuhiro Saeki1, Akira Iritani3, Tasuku Mitani3 (Dept. Genetic Eng., Kinki Univ.1, Wakayama Indust. Prom. Found.2, Inst. Adv. Technol.3) | |
| 2P073: | Functional analysis of newly identified Dictyostelium Ras genes ○Mariko Kunitani, Yoko Furuya, Tetsuya Muramoto, Hidekazu Kuwayama, Hideko Urushihara (University of Tsukuba) | |
| 2P074: | Sheet-like structure in the outer surface of egg-jelly is a key for the acrosome reaction-mediated sperm motility initiation in the internal fertilization of the newt, Cynops pyrrhogaster. ○Akihiko Watanabe, Manami Ohta, Mami Nakagawa, Kamimura Saori, Onitake Kazuo (Dept. of Biol., Fac. of Sci., Yamagata Univ.) | |
| 2P075: | Establishment of stable cell lines of male germline stem cells and their niche cells in Drosophila Shuichi Endo, ○Yuzo Niki (Ibaraki Univ. Facl. Sci.) | |
| 2P076: | Effect of NRGs and RA on spermatogonial proliferation and meiosis initiation in culture of neonatal mouse testis ○Jidong Zhang, Seiko Okuma, Ko Eto, shin-ichi Abe (GSST) | |
| 2P077: | Role of Notch signaling in PGC migration of Xenopus embryo. ○Keisuke Morichika, Kensuke Kataoka, Kenji Watanabe, Makoto Mochii (Univ. Hyogo) | |
| 2P078: | Dazl blocks the miRNA-mediated silencing of PGC-sprecific TDRD7 gene in zebrafish ○Yasuaki Takeda, Mishima Yuichiro, Sakamoto Hiroshi, Inoue Kunio (Graduate School of biology Kobe University) | |
| 2P079: | Stage-specific Importin13 activity regulates meiosis of germ cells in the mouse ○Yasuka Yamaguchi1,2, Satomi Tanaka1, Ryuichi Nishinakamura1,2, Patrick PL Tam3 (Div. of Integra. Cell Biol., IMEG, Kumamoto Univ. Kumamoto, Japan1, GCOE Kumamoto Univ. Kumamoto, Japan2, Embryology Unit, CMRI, Sydney Univ., Australia3) | |
| 2P080: | Investigating the roles of Ci-PEM in germline formation in an ascidian, Ciona intestinalis ○Maki SHIRAE-KURABAYASHI, Akira Nakamura (CDB) | |
| 2P081: | Expression of the genes implicated in the embryonic development during peri-implantation period in mouse somatic cell nuclear transfer embryos ○Masahiro Morita1, Megumi Nishiwaki1, Koshiro Moriki1, Hiroko Kawamura1, Masayuki Anzai2, Hiromi Kato2, Akira Iritani2, Yoshihiko Hosoi1, Tasuku Mitani2 (Dept. Genetic Eng., Kinki Univ.1, Inst. Adv. Technol., Kinki Univ.2) | |
| 2P082: | In vitro migration of primoedial germ cell from Xenopus tailbud embryo ○Kohei Terayama, Kensuke Kataoka, Keisuke Morichika, Hidefumi Orii, Kenji Watanabe, Makoto Mochii (Univ. Hyogo) | |
| 2P083: | Postembryonic germline specification in colonial ascidian, Botryllus primigenus ○Takeshi Sunanaga, Hironori Inubushi, Kazuo Kawamura (Fac. of Sci., Kochi Uni.) | |
| 2P084: | Genetic analysis for Wolffian duct development ○Aki Murashima1, Shinichi Miyagawa1, Ryuma Haraguchi1, Yukiko Ogino1, Shigeaki Kato2, Gen Yamada1 (CARD, Kumamoto Univ.1, IMCB, Univ. Tokyo2) | |
| 2P085: | The role of DAX1 during zebrafish embryogenesis ○Yoshifumi Yajima, Tsuruwaka Yusuke, Takagi Masahiro (JAIST) | |
| 2P086: | Analysis of the mechanism underlying the localized function of HpNanos at archenteron tip ○Takayoshi Fujii1, Naoaki Sakamoto1, Hiroshi Ochiai1, Takuya Minokawa2, Takashi Yamamoto1 (Dept.of Math. and Life Sci., Grad.School of Sci., Hiroshima Univ.1, Res. Center for Marine Bio., Grad. Sch. of life Sci., Tohoku Univ.2) | |
| 2P087: | Spermatogenic cycle may involve germ-Sertoli interplay and RA signaling in mice ○Ryo Sugimoto, Yo-ichi Nabeshima, Shosei Yoshida (Dept. Path. & Tumor Biol., Grad. Sch. Med., Kyoto Univ.) | |
| 2P088: | GFP-labeled mitochondria visualize germ plasm and primordial germ cells in Xenopus embryos ○Ayaka Taguchi, Miki Hirabayashi, Mochii Makoto, Watanabe Kenji (UNIV.HYOGO) | |
| 2P089: | Establishment of SOX9 Activation in Pre-Sertoli Cells Requires High Glucose Metabolism during Mouse Testis Formation ○Shogo Matoba1, Ryuji Hiramatsu1, Masami Kanai-Azuma2, Naoki Tsunekawa1, Kyoko Harikae1, Hayato Kawakami1, Masamichi Kurohmaru1, Yoshiakira Kanai1 (Vet. Anat. Univ.Tokyo1, Dept. Anat., Kyorin Univ. Sch. Med.2) | |
| 2P090: | Aberrant primordial germ cells migration in the embryos with defective gastrulation ○Kenshiro Hara1, Masami KANAI-AZUMA2, Naoki Tsunekawa1, Yoko Watanabe1, Yutaro Miura1, Mami Uemura1, Masamichi Kurohmaru1, Yoshiakira Kanai1 (Vet. Anat., Tokyo Univ.1, Anat. Kyorin Univ.2) | |
| 2P091: | AGING CAUSES CHANGES IN HISTONE H4 ACETYLATION AND THE EXPRESSION OF CDC2a IN METHAPHASE II AND GERMINAL VESICLE STAGES OOCYTES ○Iris Manosalva, Pedro Esponda, Clara Goday (CIB) | |
| 2P092: | Overexpression of DMRT1 can induce female-to-male sex reversal in the medaka, Oryzias latipes ○Hiroyuki Otake1, Matsuda Masaru2, Sakaizmi Mitsuru1, Hamaguchi Satochi1 (Niigata Univ.1, Utsunomiya Univ2) | |
| 2P093: | Reduced expression of a conserved RNA-binding protein by prolactin leads to apoptosis in newt spermatogonia ○Ko Eto1, Kazufumi Eda1, Motoshi Hayano1, Kenta Nagao1, Toshihiro Kawasaki1, Ai Utoguchi1, Issei Toyooka1, Hiroshi Tarui2, Osamu Nishimura2, Kiyokazu Agata2,3, SHIN-ICHI Abe1 (Kumamoto Univ.1, RIKEN CDB2, Kyoto Univ.3) | |
| 2P094: | Delayed ossification in mice with a targeted disruption of a putative protein kinase gene, AW548124 ○Yu Imuta, Noriyuki Nishioka, Hiroshi Sasaki (CDB) | |
| 2P095: | Functional analysis of a sperm factor that induces Ca increase for egg activation at newt fertilization ○Yuichirou Harada, Tamami Matsumoto, Akira Nakashima, Shuichi Ueno, Yasuhiro Iwao (Mol. Dev. Biol.,Applied Mol. BioSci.,Yamaguchi Univ.) | |
| 2P096: | A glycoprotein necessary for sperm-egg membrane binding at fertilization of the frog, Xenopus laevis ○Yasuhiro Iwao1, Keita Nagai1, Takuya Ishida1, Takafumi Hashimoto1, Yasushi Ueda1, Hideo Kubo2 (Mol. Dev. Biol.,Applied Mol. BioSci.,Yamaguchi Univ.1, Dept. Med. Biol., Tokyo Metro.Inst. Med. Sci.2) | |
| 2P097: | Biphasic subcellular localization and the role of mRNA binding protein Bruno in Drosophila spermatogenesis. ○Tatsuhiko Noguchi, Michiko Koizumi, Shigeo Hayashi (CDB RIKEN) | |
| 2P098: | Intron retention generates a novel isoform of Ceacam6 that acts as an adhesion molecule at ectoplasmic specialization between Sertoli cells and spermatids in rat testis ○Hitoshi Kurio, Emi Murayama, Takane Kaneko, Hiroshi Iida (LZGA) | |
| 2P099: | Dullard is essential for primordial germ cell formation and posterior extraembryonic mesoderm differentiation in the gastrulating mouse embryo ○Satomi S. Tanaka1, Akihiro Nakane2, Yasuka Y. Yamaguchi1,4, Sayoko Fujimura1, Makoto Asashima3, Ryuichi Nishinakamura1,4 (IMEG, Kumamoto Univ.1, Nagoya City Univ.2, Tokyo Univ.3, GCOE, Kumamoto Univ.4) | |
| 2P100: | A sex-determining gene on a medaka autosome: characterization of the XX sex-reversal mutant ○Ai Shinomiya, Hiroyuki Otake, Mitsuru Sakaizumi, Satoshi Hamaguchi (Institute of Science and Technology, Niigata Univ.) | |
| 2P101: | Nuclear accumulation of intracellular domain of TRA-2 determines somatic and germline sex-differentiation of C. elegans. Masumi Shimada1, Satomi Harukuni2, ○Hiroyuki Kawahara1 (TMU1, Hokkaido Univ.2) | |
| 2P102: | Molecular mechanisms in tongue barrier formation ○Hye-In Jung1, Sohn Wern-Joo2, Shin Hong-In3, Park Eui-Kyun3, Cho Je-Yoel1, Kim Jae-Young1, Jung Han-Sung4 (Dept of Biochemistry, School of Dentistry, Kyungpook National University, Daegu, Korea1, Center for Medical Science Research, Hallym University, Chuncheon Gangwon-do, Korea2, Dept. of Oral Pathology and Regenerative Medicine, School of Dentistry, Kyungpook National University, Daegu, Korea3, Div. in Anatomy and Developmental Biology, Dept. of Oral Biology, Research Center for Orofacial Hard Tissue Regeneration, Brain Korea 21 project, Oral Science Research Center, College of Dentistry, Yonsei Center of Biotechnology, Yonsei University, Seoul, Korea4) | |
| 2P103: | Different downstream pathways for FGF signaling are required for chondrogenic and gliogenic specification of mouse mesencephalic neural crest cells. ○Keisuke Sugiura, Kazuo Ito (Dept. of Biol. Sci., Grad. Sh. of Sci., Osaka Univ.) | |
| 2P104: | Embryonic hair follicle fate alteration by augmented β-catenin signaling relayed by Bmp receptor (BmprIA) ○Kentaro Suzuki1, yuji Yamaguchi2, Mylah Villacorte1, Kenichiro Mihara1, Masashi Akiyama3, Hiroshi Shimizu3, Makoto Taketo4, Naomi Nakagata1, Tadasuke Tsukiyama5, Terry Yamaguchi6, Shigeaki Kato7, Walter Birchmeier8, Gen Yamada1 (CARD1, Nagoya City Univ.2, Dep. of Dermatology, Hokkaido Univ.3, Dep. of Pharmacology, Kyoto Univ.4, Dep.t of Molecular Biochemistry, Hokkaido Univ.5, NIH6, IMCB,Univ. of Tokyo7, Dep. of Cancer Biology, Max-Delbrück-Center8) | |
| 2P105: | Downstream signaling of the Notch receptor diverges into two distinct pathways via its selective endocytic trafficking mediated by Deltex ○Kenta Yamada, Kazuya Hori, Takashi J. Fuwa, Kenji Matsuno (Dept. Biol. Sci. / Tec., Tokyo Univ. Sci.) | |
| 2P106: | Interaction between Zic function and Wnt signaling in vertebrate development ○TAKAHIKO J. Fujimi, Tahashi Inoue, Jun Aruga (BSI) | |
| 2P107: | Roles of Wntless in zebrafish development ○Qiuhong Chen, Shinji Takada (Dept.Mol.Dev.NIBB) | |
| 2P108: | Functions of a neurogenic gene, pecanex in Notch signaling ○Tomoko Yamakawa, Takeshi Sasamura, Maiko Kanai, Kenji Matsuno (Dept. Biol. Sci./Tec. Tokyo Univ of Sci.) | |
| 2P109: | Identification and characterization of a transgene insertion mutation of Ext2 gene encoding a glycosyltransferase Kazuhiro Mukai1,2, Chiharu Kimura-Yoshida1, Saori Amazaki1, Kayo Shimokawa1, ○Isao Matsuo1,2 (Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health1, Osaka University Graduate School of Medicine2) | |
| 2P110: | Essential role of serum- and glucocorticoid-inducible kinase 1 (SGK1) in early Xenopus development ○Tatsuya Endo, Morioh Kusakabe, Kazunori Sunadome, Takuya Yamamoto, Eisuke Nishida (Graduate School of Biostudies, Kyoto University) | |
| 2P111: | Wnt signalling in the endoplasmic reticulum of early Xenopus embryos ○Eriko Motomura1, Yuya Nasu1, Tomohiro Narita2, Ayako Sedohara3, Shin-ichiro Nishimatsu2, Tsutomu Nohno2, Hidefumi Fujii1, Masao Sakai1 (Dept. Chem and Biosci., Fac. Sci. Kagoshima Univ.1, Department of Molecular Biology, Kawasaki Medical School2, Department of Life Sciences (Biology), Graduate school of Art and Sciences, University of Tokyo3) | |
| 2P112: | Wnt dependent and independent cell polarization during asymmetric divisions in C.elegans ○Yuko Yamamoto1,2, Hisako Takeshita1, Hitoshi Sawa1,2 (RIKEN CDB, Dep. of Biol.,1, Grad. Sci., Kobe Univ.2) | |
| 2P113: | Expression analysis of Hoxb5 in enteric neurons and generation of tamoxifen inducible Cre mice for neuronal Hoxb5 signaling perturbation ○Mandy KM Kam, William WC Cheng, Paul KH Tam, Vincent CH Lui (HKU) | |
| 2P114: | Conditional Ptc1 knockout in vagal neural crest cells causes a reduced proliferation of enteric nervous system progenitors and intestinal hypoganglionosis ○Tracy HC Poon1, Elly SW Ngan1, Francesco YL Sit1, Chi C Hui2,3, Brandon J Wainwright4, Mai H Sham5, Paul KH Tam1, Vincent CH Lui1 (Department of Surgery, LKS Faculty oMedicine, The University of Hong Kong1, Program in Development & Stem Cell Biology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto2, Department of Molecular and Medical Genetics, University of Toronto3, Institute for Molecular Bioscience, The University of Queensland4, Department of Biochemistry, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong5) | |
| 2P115: | Regulation of Notch trafficking and activation by Nedd4 family of ubiquitin ligases ○Koji Kawahashi1,2, Tadashi Sakata1, Shigeo Hayashi1,2 (Grad. Schl. Sci. Tech., Kobe Univ.1, RIKEN CDB2) | |
| 2P116: | Microarray analysis of endoderm specific genes ○Seiko Harada, Nobuaki Shiraki, Kazuhiko Kume, Shoen Kume (Div. of Stem Cell Biol, IMEG, Kumamoto Univ.) | |
| 2P117: | The role of cytokinin in Dictyostelium development ○Masashi Fukuzawa, Hiroshi Senoh, Kohei Tanaka (Faculty of Agriculture and Life Science, Hirosaki University) | |
| 2P118: | Screening for point mutations in Hedgehog signaling genes, Smoothened and Sufu, from the ENU-mutagenized mouse genome archive ○Shigeru Makino1,2, Yoshiyuki Sakuraba2, Hayato Kotaki2, Taichi Yamaguchi2, Takuya Murata1,2, Ryutaro Fukumura1,2, Yuji Nakai1,2, Kaori Takenouchi2, Hideki Kaneda1,2, CHI-CHUNG Hui3, Shigeharu Wakana1,2, Tetsuo Noda1,2, Toshihiko Shiroishi2, Yoichi Gondo1,2 (RIKEN BRC1, RIKEN GSC2, Sickkids3) | |
| 2P119: | Two GFP-fucose transporters, one localizes to endoplasmic reticulum (ER) and the other to Golgi, have redundant roles for the O-fucosylation of Notch ○Tomonori Ayukawa1, Ishikawa Hiroyuki2, Ishida Nobuhiro3, Aoki Kazuhisa3, Sanai Yutaka3, Kamiyama Jin4, Nishihara Syoko4, Matsuno Kenji1,2 (Dept.of Biol.Sci.& Technol., Tokyo Univ.of Sci.1, Genome and Drug Research Center Tokyo University of Science,2, Department of Biochemical Cell Research, The Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science3, Laboratory of Cell Biology, Department of Bioinformatics, Faculty of Engineering,, Soka University4) | |
| 2P120: | Identification of stem cells in the lens epithelial cells ○Mikako Oka, Chizuko Toyoda, Eriko Yokota, Makoto Takehana (Keio Univ Facult of Pharmacy) | |
| 2P121: | Roles of hedgehog signaling in Ciona intestinalis development: insights from hedgehog and Gli expression and cyclopamine treatment ○A. F. M. Tariqul Islam, Pricila Khan Moly, Yuki Miyamoto, Takehiro G. Kusakabe (Grad. Sch. Life Sci., Univ. Hyogo) | |
| 2P122: | Nerve-dependent regulation of the the cell cycle and induction of the regeneration-competent wound epidermis ○Akira Satoh, Susan Bryant, David Gardiner (UCI) | |
| 2P123: | Analysis of the relation between regenerative ability and immune response in the Xenopus tadpole tails ○Taro Fukazawa, Takekazu Kunieda, Takeo Kubo (Dept.Biol.Sci,Grad.Sch.Sci,Univ.Tokyo) | |
| 2P124: | The Balance Between Self-Renewal and Differentiation in Drosophila Neuroblasts Undergoing Symmetric Division ○Atsushi Kitajima1, Naoyuki Fuse2, Takako Isshiki3, Fumio Matsuzaki1 (Cell Asymmetry, RIKEN CDB1, Division of Gene Expression, NIG2, Laboratory for Cell Lineage, NIG3) | |
| 2P125: | Gene expression profile of zebrafish hematopoietic stem cells ○Isao Kobayashi1,2, Hiromasa Ono3, Tadaaki Moritomo4, Kano Koichiro4, Nakanishi Teruyuki4 (Grad. sch. of Vet. Med., Nihon Univ.1, JSPS Research Fellow2, Grad. sch. of Bior. Sci., Nihon Univ.3, Coll. of Bior. Sci., Nihon Univ.4) | |
| 2P126: | The mechanism regulating the red blood cell transition from larval to adult type during metamorphosis of Xenopus laevis ○Masahiro Yamaguchi, Tsutomu Kinoshita (Dept. Biosci., Sch. Sci. Technol., Kwansei Gakuin Univ.) | |
| 2P127: | Derivation of embryonic stem cells from rabbit embryos. ○Syunsuke Ito1, Ryo Kakegawa2, Toshiyuki Takehara2, Naoto Fukunaga1, Yuki Miyamoto1, Yoshiko Tsujimoto1, Satoshi Kishigami1, Kazuya Matsumoto1, Kazuhiro Saeki1, Akira Iritani1, Yoshihiko Hosoi1 (Dep. B.O.S.T. Kinki Univ1, Gra. sch. B.O.S.T. Kinki Univ2) | |
| 2P128: | Functional expression cloning of HP1 beta, a modulator of differentiation in embryonic stem cells and embryonal carcinoma cells. ○Nobuhito Ikeda1, Shinjiro Kawazoe1,2, Masayuki Shibuya1, Kengo Miki3, Ichiro Hisatome1, Yasuaki Shirayoshi1 (Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Tottori University1, Physiology and Regenerative Medicine, Mie University2, School of Life Science, Tottori University3) | |
| 2P129: | Establishment of embryonic stem cell lines derived from MSM/Ms strain originated from Mus musculus molossinus. ○Kimi Araki1, Naoki Takeda2, Yoshiki Atsushi3, Yamada Gen2, Nakagata Naomi2, Shiroishi Toshihiko4, Moriwaki Kazuo3, Yamamura Ken-ichi1 (Kumamoto Univ., IMEG1, IRDA, Kumamoto Univ.2, Riken Bioresourse3, NIG4) | |
| 2P130: | Expression of Bcrp1 mRNA isoforms during in vitro differentiation of mouse embryonic stem cells ○Hiroko Kawamura1, Noki Amimoto1, Koushirou Moriki1, Masahiro Morita1, Masayuki Anzai2, Hiromi Kato2, Yoshihiko Hosoi1, Akira Iritani2, Tasuku Mitani2 (Dept. Genetic Eng., Kinki Univ.1, Inst. Adv. Technol., Kinki Univ.2) | |
| 2P131: | Fat signaling and Hippo pathway are required for cell proliferation and proper proximodistal regeneration of amputated legs in the cricket, Gryllus bimaculatus ○Tetsuya Bando1, Yuko Maeda2, Fumiaki Ito2, Taro Nakamura2, Taro Mito2, Hideyo Ohuchi1,2, Sumihare Noji1,2 (Tokushima Intellectual Cluster1, Dept. of Life System, Inst. of Technology and Science, Univ. of Tokushima2) | |
| 2P132: | Investigation of asymmetric localization of Wnt signaling components in mammalian cells ○Takashi Yano, Hitoshi Sawa (Lab. for Cell Fate Decision, RIKEN CDB) | |
| 2P133: | Molecular mechanisms of proximodistal patterning during leg regeneration in the cricket, Gryllus bimaculatus ○Taro Nakamura1, Taro Mito1, Bando Tetsuya2, Ohuchi Hideyo1,2, Noji Sumihare1,2 (Department of life system, The Univ. of Tokushima1, Tokushima Intellectual Cluster2) | |
| 2P134: | FERM domain proteins, Expanded and Merlin regulate cell proliferation and proper longitudinal regeneration of amputated legs of cricket, Gryllus bimaculatus ○Fumiaki Ito1, Tetsuya Bando2, Yuko Maeda1, Taro Nakamura1, Taro Mito1, Hideyo Ohuchi1,2, Sumihare Noji1,2 (Dept. of Life System, Inst. of Tech. and Sci. Univ. of Tokushima1, Tokushima Intellectual Cluster2) | |
| 2P135: | Gemmule formation of freshwater sponge; a new system for analyzing resting state entry of stem cells. ○Kurato Mohri, Kiyokazu Agata, Noriko Funayama (Molecular Developmental Biology, Dept. of Biophysics, Grad. Shool of Sci., Kyoto Univ.) | |
| 2P136: | Guided differentiation of ES cells into pancreatic endocrine precursors ○Yuichiro Higuchi, Nobuaki Shiraki, Kimi Araki, Kazuhiko Kume, Shoen Kume (IMEG) | |
| 2P137: | Analysis of the transcription factor network that controls trophoblast differentiation ○Kenjiro Adachi, Hitoshi Niwa (RIKEN・CDB) | |
| 2P138: | Dynamic response of DNA repair factors to artificial DNA damage in mouse germinal stem cell ○Suzu Sakao1, Satoshi Tateishi2, Haruna Yamamoto3, Saori Ito3, Kentaro Yomogida3 (RCEND, Mukogawa Women's Univ.1, Inst Mol Embryol Genet, Kumamoto Univ2, Grad Sch Human Environ Sci, Mukogawa Women’s Univ3) | |
| 2P139: | Molecular dissection of the early steps of planarian regeneration ○Junichi Tasaki1, Yoshihiko Umesono1, Kazu Itomi2, Osamu Nishimura2, Yoshimichi Tabata3, Fuyan Son3, Nobuko Suzuki3, Ryoko Araki3, Masumi Abe3, Kiyokazu Agata1 (Department of Biophysics Graduate School of Science, Kyoto University1, Center for Developmental Biology, RIKEN2, Transcriptome Research Center, National Institute of Radiological Sciences3) | |
| 2P140: | The induction of mesoderm linage by culturing on the matrix of extraembryonic endoderm derived from mouse ES cells ○Kazuhiro Murakami, Daisuke Shimosato, Hitoshi Niwa (RIKEN, CDB, PCS) | |
| 2P141: | The characterization of liver progenitor during embryonic development and liver injury ○Akira Matsuo, Tetsu Yoshida, Kazuhiko Kume, Shoen Kume (Divison of Stem Cell Biology, Department of Regeneration Medicine IMEG) | |
| 2P142: | Formation of the carbohydrate- and E-cadherin-enriched membrane microdomain is crucial in epiboly during gastrulation of medaka Tomoko Adachi1, Chihiro Sato1,2, ○Ken Kitajima1,2 (Nagoya Univ. Biosci. Biotech. Ctr.1, Grad. Sch. Bioagr. Sci., Nagoya Univ.2) | |
| Luncheon seminars |
|
Invitation of applications for the Luncheon Seminars. (Registration fee: 300,000 yen + lunch for profitable organizations) (Registration fee: Lunch for non-profitable organizations) |
| 28 May, 12:10 - 13:00 |
|
Lunchoen 1: 会場: B会場 スポンサー: (株)ニコンインステック 演者: 永井 健治 (北海道大学電子科学研究所) |
| 30 May, 12:10 - 13:00 |
|
Lunchoen 2: iPS細胞の現状(仮) 会場: B会場 スポンサー: Aloka Co. Ltd. (アロカ(株)) 演者: 小柳 三千代 (京都大学再生医科学研究所再生誘導研究分野) |
| Gender-equal society (in Japanese) |
| 29 May, 12:10 - 13:00, 先着100名に弁当を用意致します。 |
|
「男女共同参画とポスドク問題の現状:アンケート調査結果から学ぶ」 オーガナイザー: 田中 仁夫(徳島大学), 野呂 知加子(日本大学) 会場: B会場 |
|
平成18年度より、国の予算に女性研究者支援関連事業費が充当され、科学技術分野での男女共同参画が推進されつつある。一方で、いわゆるポスドク問題にも関心が高まり、国の予算にも若手研究者支援のためのテニュアトラックやイノベーション創出人材育成などの施策が盛り込まれるようになった。本ワークショップオーガナイザーの田中仁夫自身も博士研究員のキャリアパス問題に取り組むべく大学発ベンチャーでの起業を行っている。このような問題に取り組むためには、まず正確な現状の把握と認識が必要である。 平成19年度、理工系の学会の集まりである男女共同参画学協会連絡会によって行われた科学技術系専門職の男女共同参画実態調査のための大規模アンケートでは、発生学会会員の皆様に積極的にご回答いただいた(正式加盟学会中では回答率が1位!)。集計を担当された幹事学会の生物物理学会によれば、この調査により現状における男女共同参画およびポスドク問題の様々な問題が浮き彫りにされたそうである。集計という大変な役割を担当された豊島陽子先生から、この問題にフォーカスしたお話をいただく。 一方文部科学省科学技術政策研究所では、平成17年度にポスドク雇用状況調査を行ったが、この年ポスドクとして雇用されたのは1万5496人であり、そのうち女性の割合は21.4%であることが分かった。この調査を担当された三浦有紀子先生から、ポスドクの現状とその問題点についてお伺いしたい。 短い時間ではあるが、参加者を含めて活発な論議をいただき、これらの問題について考える機会になればと期待している。 1. 「はじめに」 野呂 知加子 (日本大学) 2. 「男女共同参画およびポスドク問題について; 科学技術系専門職の男女共同参画実態調査のためのアンケート結果より」 東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻生命環境科学系 豊島 陽子 3. 「博士号取得者のキャリアパス」 社団法人日本物理学会キャリア支援センター 三浦 有紀子 (予定) 4. 「ディスカッションと総括」 田中 仁夫(徳島大学) |
| Satellite workshops organized by junior members (in Japanese) |
| 27 May, 17:00 - 21:00 |
|
SW1: 形態形成のダイナミズム オーガナイザー: 布施 直之(遺伝研), 影山 裕二(基生研) 会場: B会場 |
| SW1-01: | 上皮形態を制御する短鎖ペプチド ○近藤 武史, 橋本 祥子, 影山 裕二 (基生研/奈良先端大) | |
| SW1-02: | EGFRシグナルの伝播はショウジョウバエ気管前駆細胞の配列と再配置のパターンを決定する ○西村 真由子1, 井上 淑子1,2, 林 茂生1 (理研CDB1, 現所属: Univ. of Cambridge2) | |
| SW1-03: | アフリカツメガエル原腸形成運動における細胞極性形成 ○進藤 麻子, 山本 隆正, 上野 直人 (基生研) | |
| SW1-04: | マウス精巣における生殖幹・前駆細胞の分化の時空間的制御 ○杉本 亮, 鍋島 陽一, 吉田 松生 (京大・院・医) | |
| SW1-05: | ショウジョウバエ原腸陥入を制御するシグナル伝達機構 ○布施 直之, 広瀬 進 (遺伝研) | |
| SW1-06: | 二光子顕微鏡を用いたライブイメージング法による血管系形成過程の解析 ○木村 英二, 谷藤 吾朗, 磯貝 純夫, 人見 次郎 (岩手医大) | |
| SW1-07: | 脊椎動物における形態形成の生体イメージング解析:左右の脳の境界を越えて移動する神経、神経上皮と神経堤細胞 ○八田 公平, 磯田 恵里佳, 山本 珠実, 伊藤 真理子, 中山 創平, Pricila Khan Moly (兵庫県立大) | |
|
SW2: ツメガエルが拓く胚発生・形態形成研究の新展開 オーガナイザー: 渡部 稔(徳島大学・総合科学・自然システム) 会場: C会場 |
| SW2-01: | ゼノパス初期胚ではWntは小胞体で働く ○本村 恵理子1, 成田 知弘2, 坂井 雅夫1 (鹿児島大学・院理工・生命化学1, 川崎医科大学・分子生物2) | |
| SW2-02: | 分泌性Frizzled関連蛋白質Frzb1及びCrescentの細胞外相互作用によるWnt拡散性の変化 ○三井 優輔, 平良 眞規 (東京大学・院理・生物科学) | |
| SW2-03: | 誘導と自律分化によるセメント腺形成:BMP-3bとBMP-3の相違 ○西松 伸一郎1, 日野 純2, 寒川 賢治2, 松尾 壽之2, 濃野 勉1 (川崎医大・分子生物1, 国立循環器病セ・研・生化学2) | |
| SW2-04: | BMP/Chordin系によるDVパターンの頑強性の分子機構について ○猪股 秀彦 (理研CDB・細胞分化・器官発生) | |
| SW2-05: | ツメガエル心臓形成関連遺伝子XHAPLN3の機能解析 ○伊藤 弓弦1, 福井 彰雅2, 浅島 誠1 (東京大学・生命科学構造化センター1, 北海道大学・院理・生命理学2) | |
| SW2-06: | ツメガエル胚の形態形成を細胞内動態から理解する-神経管閉鎖におけるMIDの機能解析を通して- ○鈴木 誠1,2, 上野 直人1 (基生研・形態形成1, 学振特別研究員2) | |
| SW2-07: | 透明化割球を用いた細胞周期位相の可視化と細胞周期伸長機構の解析 ○上野 秀一 (山口大学・院医・応用分子生命) | |
| SW2-08: | FoxM1依存の細胞分裂はツメガエル神経分化に必要である ○上野 裕之1, 中條 信成1, 渡部 稔2, 磯田 道孝1, 佐方 功幸1 (九大・院理・生物科学1, 徳島大・総合科学・自然システム2) | |
| SW2-09: | ツメガエルW染色体上のDM-Wは初期卵巣形成において Foxl2とアロマターゼ遺伝子の発現を誘導する ○吉本 真1, 岡田 絵真1, 神田 宏美1, 田村 啓1, 宇野 好宣2, 西田-梅原 千鶴子2, 松田 洋一2, 柴 忠義1, 高松 信彦1, 伊藤 道彦1 (北里大学・理・生物情報科学1, 北海道大学・創成科学2) | |
| SW2-10: | 生殖細胞決定因子であるgerm plasmに局在するmRNAの単離と機能解析 ○谷川 葉子, 池西 厚之, 小宮 透 (大阪市立大学・院理・動物機能学) | |
| SW2-11: | Xenopus tropicalis用いた研究の現在の状況と将来の方向性について ○荻野 肇 (奈良先端大学院大・バイオサイエンス) | |
|
SW3: 多分野で活躍する小型魚類 オーガナイザー: 越田 澄人(東京大学), 伊藤 素行(名古屋大学) 会場: D会場 |
| SW3-01: | 赤血球はどうやってできるのか ○竹内 未紀1, 金子 寛1, 小林 麻己人1, 山本 雅之2 (筑波大・人間総合1, 東北大・医2) | |
| SW3-02: | 体節形成におけるNotchシグナル依存的な転写に酵母Paf1複合体ホモログが働いている ○赤沼 啓志1, 越田 澄人1, 岸本 康之2, 川村 哲規1, 高田 慎治1 (自然機構・岡崎統合バイオ1, 遺伝研2) | |
| SW3-03: | 腎疾患モデルとしてのメダカ ○橋本 寿史, 渡辺 直樹, 若松 佑子 (名古屋大学生物機能開発利用研究センター) | |
| SW3-04: | Nemo-like kinaseはNotchシグナルを阻害し、神経分化を制御する ○石谷 太1,2,3, 平尾 智子1, 鈴木 真帆2, 磯田 美帆1, 松本 邦弘2, 伊藤 素行1 (名古屋大学高等研究院(理学研究科) 神経形成シグナル学1, 名古屋大学大学院 理学研究科 生命理学専攻 生体調節論 生体応答論講座2, 九州大学生体防御医学研究所3) | |
| SW3-05: | ゼブラフィッシュmiRNA制御システムによる生殖細胞形成機構 ○井上 邦夫 (神戸大学大学院理学研究科生物学専攻) | |
| SW3-06: | 小型魚類研究の新ツールの紹介-メダカTILLING法と赤外レーザ単一細胞遺伝子発現系- ○亀井 保博1, 石川 智子1, 音在 信治1, 藤堂 剛1, 高木 新2, 鈴木 基史2, 船津 高志3, 弓場 俊輔4 (阪大・院・医1, 名大・院・理2, 東大・院・薬3, 産総研・セル4) | |
| SW3-07: | ゼブラフィッシュGal4トラップ法を用いた神経回路の可視化と機能阻害 ○浅川 和秀1, Maximiliano L. Suster1, 浦崎 明宏1, 小谷 友也1, 永吉 さおり1, 岸本 康之1, 日比 正彦2, 川上 浩一1 (遺伝研1, 理研CDB2) | |
| SW3-08: | 繊毛関連疾患モデルとしてのゼブラフィッシュとTAP法を用いたプロテオミクス解析 –IFTとRab GTPaseの相互作用による繊毛局在タンパクの輸送機構 ○大森 義裕1,2, 古川 貴久1, Jarema Malicki2 (大阪バイオサイエンス研究所、発生生物学部門1, Harvard Medical School, Department of Ophthalmology2) | |
|
SW4: Molecular Mechanisms of the Vertebrate Brain Evolution Organizers: Yasunori Murakami (Ehime Univ.), Eiji Matsunaga (RIKEN BSI) Room: E |
| SW4-01: | Development of the lamprey nervous system: with reference to the vertebrate brain evolution ○Yasunori Murakami, Aki Watanabe (Department of Biology, Faculty of Science, Ehime University) | |
| SW4-02: | Evolution of Vertebrate Otx2 enhancers -from Skate to Mouse- ○Daisuke Kurokawa (Misaki marine biological station, Tokyo University. Lab for Vertebrate Body Plan, RIKEN CDB) | |
| SW4-03: | Molecular insights into the cerebellar-like structures ○Yu Katsuyama (Kobe University Graduate School of Medicine) | |
| SW4-04: | Evolution and diversity in avian vocal system ○Eiji Matsunaga, Kazuo Okanoya (Lab for Biolinguistics, RIKEN BSI) | |
| SW4-05: | Mammalian brain evolution caused by SINE insertion ○Takeshi Sasaki, Norihiro Okada (Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology) | |
| SW4-06: | Migrating cells and signaling centers. ○Alessandra Pierani, Amélie Griveau, Anne Teissier, Sonia Karaz, Causeret F (Institute Jacques-Monod, Paris) | |
| SW4-07: | Comparative molecular neuroanatomy of mammalian neocortex: what are areas and layers? ○Akiya Watakabe (Division of brain biology, National Institute for Basic Biology) | |
| SW4-08: | What does comparative genomics tell us about the evolutionary elaboration of the brain? ○Hitoshi Okamoto (Laboratory for Developmental Gene Regulation, RIKEN Brain Science Institute) | |
| Public lectures (in Japanese) |
| 市民公開講座: | 発生生物学から見た生物の世界 |
| 日時: | 平成20年5月31日(土) 13:00~16:00 |
| 会場: | 徳島県郷土文化会館1階ホール |
| 世話人: | 渡部 稔(徳島大学総合科学部) |
| 後援: | 徳島県教育委員会、徳島市教育委員会、NHK徳島放送局、徳島新聞社 |
| 参加料: | 無料(事前参加登録の必要はありません。当日ご自由にご参加ください) |
| 第41回日本発生生物学会年大会では、次世代の生命科学研究を担う中学・高校生や、生物や生き物の不思議に興味のある一般の方々を対象とした公開講座を開催いたします。 基礎的研究から応用研究まで、生物学研究の世界について分かりやすく紹介し、研究の魅力をお伝えします。参加は無料です。たくさんの方のご来場をお待ちしております。 |
| 1. サカナの異常から見えてくる人の病気 |
| 平田 普三 (名古屋大学理学研究科) |
| サカナと人間は外見は違うけれど、同じ脊椎動物であり、循環器系、消化器系、神経系、運動系など多くの部分で共通のシステムをもっています。熱帯魚として親しまれているゼブラフィッシュは生物学研究に有用で、遺伝病をもつもの(変異体)が多数あります。中には見た目には正常だけれど、運動機能に異常のあるものもあり、研究により神経や筋の異常が見つかります。これらの異常は人の遺伝性の神経疾患や筋疾患と同じものであり、サカナの研究から人の難病が見えてくるのです。 |
| 2. シマウマはなぜ縞を持っているのか? |
| 近藤 滋 (名古屋大学理学研究科) |
| 動物には、きれいな模様を持っているものがたくさんいますが、なぜだと思いますか?例えばシマウマの縞模様。どう見ても目立ちすぎです。あれじゃ、ライオンに直ぐに見つかってしまいます。「縞模様は目くらましになる!」という説明もあるのですが、野生を紹介するTVを見ている限りでは、役に立っているようには見えません。では、どうやって縞模様は進化してきたのでしょう?さて、ここで天才数学者チューリングが登場します。彼は1952年に「動物の皮膚模様は波である」という驚くべき仮説を出しました。そして50年後、皮膚模様が本当に「波」であることが証明されました。チューリングの理論を使えば、シマウマがなぜ縞模様を持っているのかがわかります。そのアッと驚く答えは、、、、、、会場で。 |
| 3. クロマグロ完全養殖への挑戦 |
| 熊井 英水 (近畿大学水産研究所) |
|
日本人が利用しているマグロは5種あり、中でもクロマグロは海のダイヤとも呼ばれ、大きさ、味覚、市場価格共に最高位を誇る。しかしマグロ類中での漁獲割合は僅か1.8%にすぎない。 私共はこの貴重で希少な本種に注目して1970年から増養殖の研究を開始した。本種は酸素要求量が大きく、皮膚が脆弱で稚魚期には共喰が激しく光や音などの刺戟に敏感で、その上濁水にも弱く、飼育の極めて困難な魚種である。私共はこれらの困難を克服して1979年初めて生簀内での産卵に成功し、2002年6月には実に32年の歳月を要したが、世界で初めて本種の「完全養殖」に成功した。さらに2007年6月にはこの完全養殖から生まれた子供が5年経ち親魚となって産卵を開始し、人工ふ化クロマグロ第3世代が誕生した。 |